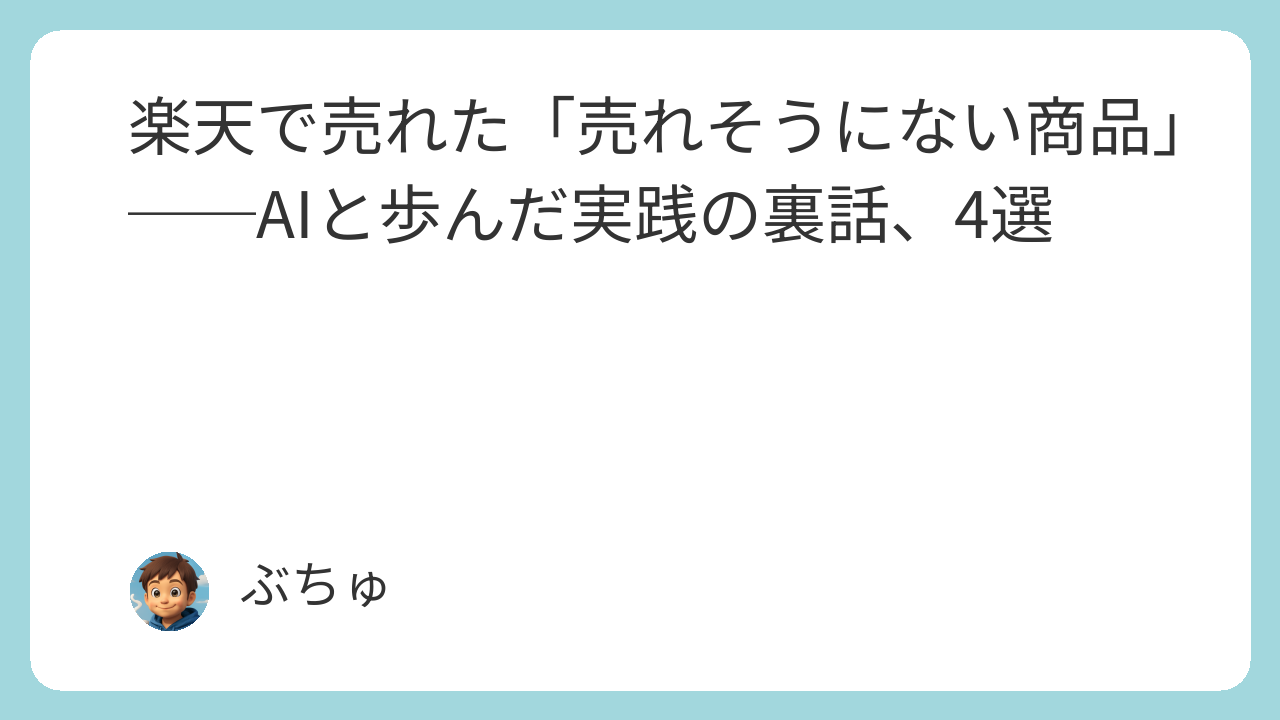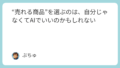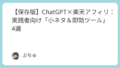こんにちは、ぶちゅです。
今回は、僕自身の楽天アフィリ実践の中から
**「リアルな体験談 × AI活用」**を軸にした、
ちょっと不思議で、ちょっとヒントになる話を4つシェアします。
どれも最初はうまくいっていません。
でも、だからこそ伝えられることがあると思うんです。
「売れそうにない商品」がなぜか売れた日
ある日、楽天アフィリで**初めて「1件売れた通知」が来た**んです。
正直、その瞬間は小さなガッツポーズが出るくらい嬉しかったのを覚えています。
でも、リンクを確認して商品の詳細を見た時、思わず「え、これが?」と声が出ました。
レビューは★3前後と平均的で、口コミもパッとせず、
画像も「昔ながらのネット通販感」が強めで、オシャレさには欠ける商品。
「これは正直…自分でも買わないかも…」と本音が漏れそうになりました。
なぜ売れたのか。とにかく記事を見返しました。
改めて読んで気づいたのは、商品紹介そのものではなく、
“読者の使いどころ”に寄り添った一文の存在でした。
「ちょっとした贈り物や、自分用の“気分転換”にちょうどいいかもしれません」
この一文が、まさに読者の気持ちに刺さったのかもしれません。
商品を“評価”するのではなく、“誰にどんなシーンで使えるか”を想像して書く。
スペックよりも、読者の暮らしや感情に寄り添った表現の方が、時に力を持つのだと実感しました。
実際、この出来事をきっかけに、「商品の見た目や評判にとらわれすぎないこと」や、
「自分の視点ではなく、読者の状況に立った言葉選びをすること」の大切さを学びました。
それ以来、少しでも“読者の頭の中にある使い道”に寄り添ったフレーズを入れるよう意識しています。
売れるかどうかはコントロールできないけれど、届く言葉は選べるんだなと。
この経験が、僕の「書き方」と「商品を見る視点」を変える大きな分岐点になりました。
セール直前にネタがなくてAIに泣きついた
楽天のスーパーセール3日前。
「目玉商品系の記事を書かないと…でも、書くネタが浮かばない…」
と完全にフリーズしてしまった時期がありました。
それまで毎回、自分でトレンドを調べたり、楽天ランキングを眺めたりして
「この商品が売れそうかな」とアタリをつけてきたんですが、
この時はなぜか、全くピンと来るものがなかったんです。
セール直前の“やらなきゃ感”と、“何も思いつかない焦り”が重なって、
PCの前で数時間が経過。
苦し紛れにChatGPTにこう聞きました:
「楽天スーパーセール直前に注目されやすいジャンルや商品例を教えて」
すると、
・駆け込み需要(季節家電・ファッション)
・セール後に使いたい収納グッズや日用品
など、具体的なシーン別の提案とともに、読者心理に沿った切り口が返ってきました。
たとえば、
「今買えば、週末に間に合う〇〇」や、
「増税前にまとめ買いしたい日用品5選」など、
“今動く理由”を感じさせるアイデアが詰まっていたんです。
そのままタイトルを3つ作ってもらい、
それぞれにサブキャッチと導入文もセットで依頼して、
一番しっくり来た構成をそのまま流用して記事を投稿。
結果、その中の1本がセール期間中に**クリック率5.2%**を記録。
僕の中では「当たった」と言える手応えでした。
もしあのときAIに頼っていなかったら、
空回りして何も投稿できずに終わっていたかもしれません。
**「もう無理…」って時のAIは、マジで救世主**です。
上位表示したのに全然売れない→「見せ方」改善で復活
ある商標記事で、Google検索4位に入りました。
それまでの積み重ねが報われたような気がして、正直めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えています。
「よし!これで売れるぞ!」とウキウキして、アナリティクスの数字をチェックしながら待っていたんですが……
**1件も売れない。**
アクセスは日を追うごとに増えていき、検索流入も安定してきていたのに、
なぜか楽天リンクのクリックが少なく、クリックされても購入につながらない。
読者は来るのに、買わない。これはなぜなんだ?と、本当に悩みました。
「コンテンツの中身が悪いのか?」
「そもそもこの商品、ニーズがなかったのか?」
そうやって自問自答を繰り返す中で、ふとChatGPTに聞いてみることにしました。
「この商品のメリットが伝わるように、違う見せ方を考えて」
すると、AIから返ってきたのは、
・比較表で“差”を見せる
・「誰に向いてるか」で先に共感させる
・レビューから“意外な用途”を掘り出す
といった、実践的でしかも“納得感のある提案”でした。
とくに刺さったのは、「その商品が“誰にとってベストか”を明確にすること」。
自分では商品の機能や価格ばかりに目が行っていましたが、
読者が本当に知りたいのは「自分にとってアリかナシか」という判断軸だったんです。
そこで、記事の冒頭に“こんな人におすすめ”というボックスを追加し、
レビューから抜き出した「思っていたより軽くて驚いた」「使い方が簡単」という声を紹介。
さらに、他社商品との比較表も作って、“差”を一目で見せられるようにしました。
こうした工夫を加えてから数日後──
**初めて「同じ商品が2個売れた」通知**が届きました。
その瞬間、思わずガッツポーズ。
上位表示はあくまで「スタート地点」であって、
そこから先は「どう伝えるか」で結果がまったく変わるんだ、と実感しました。
**見せ方を磨くと「読者の反応」が一気に変わる。**
これは理屈じゃなく、実際に体験してみて初めて腹落ちした教訓です。
「ジャンル特化」に縛られて動けなくなった日
「商標系はジャンル特化がいい」
そう信じて、家電だけ、ガジェットだけ、とテーマを絞って運営していました。
最初のうちは「一貫性があるし、検索でも強くなる」と感じていたのですが、
数ヶ月が経つ頃には、ネタの枯渇と向き合うことになりました。
「このジャンル、もうレビューする商品が尽きてきた…」
「無理やり記事を書く感じになってて、筆も止まる…」
そんな状態が続いていて、更新のモチベーションも低下。
「このジャンル縛り、正直きついな…」という思いが心の中で膨らんでいきました。
でも“ジャンルを変える=方針ブレる=ダメ”みたいな固定観念があり、動けずにいたんです。
そんなとき、ふとAIにこう聞いてみました。
「今のサイトの方向性を活かしつつ、無理なく続けられるジャンル構成ってある?」
返ってきたのは意外にも柔軟な提案:
「“暮らしの中で使う実用品”を切り口にすれば、家電も雑貨も日用品も扱えるのでは?」
その一言で視界が一気に広がりました。
「なるほど、“用途”や“生活シーン”で括ればいいんだ」
と、無理に“カテゴリ”でまとめる必要はないと気づいたんです。
それ以来、収納グッズやキッチン用品、在宅ワーク向け文具など、
「暮らしの中で役立つもの」をテーマに幅を広げてみました。
すると、不思議なことにネタが尽きにくくなり、
「これも書ける、あれも紹介できる」と発想が前向きに。
少しずつ他ジャンルの記事も書けるようになり、
結果的に更新頻度も戻ってきました。
「ジャンルを緩めるとサイトがブレる」わけではなく、
“切り口”が通っていればちゃんと世界観は保てる。
今ではむしろ、雑貨や日用品の方が売れ筋になることも増えて、
収益的にも安定感が出てきました。
無理して特化を貫くよりも、続けられる柔軟さの方がずっと大事。
この体験は、運営スタイルそのものを見直す大きな転機になりました。
まとめ:リアルな試行錯誤にこそ、価値がある
今回の体験談で伝えたいのは、
うまくいかない時こそ、「AI」と「ちょっとした視点の転換」が効くということ。
そして、誰にでも「変な売れ方」や「意外な突破口」はあるんです。
あなたの中にも、まだ形になってない“リアルな物語”がきっとあるはず。
それが、次の1クリック、1成約につながるヒントになります。
引き続き、一緒に試行錯誤していきましょう!