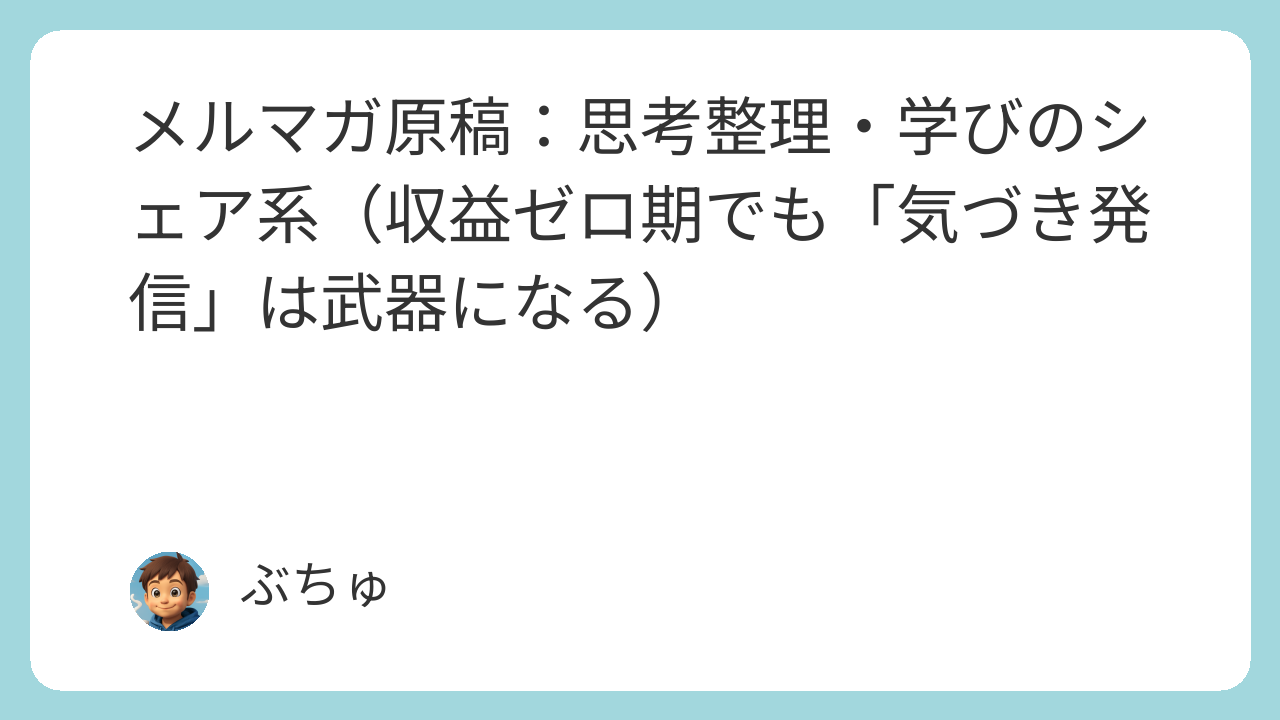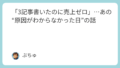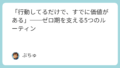こんにちは、ぶちゅです。
今回は、**「収益ゼロ期でも、気づきを発信することの価値」**について、最近の自分の試行錯誤やAIとのやりとりを通じて感じたことをシェアさせてください。
売れない時期って、「やってても意味あるのかな…」と不安になりますよね。
そんな時期こそ、自分が考えていることや学んだこと、つまずいたことをアウトプットしていくことで、「気づき」が自分の財産になり、未来の資産記事につながると感じています。
特に最近は、AIと対話しながら考えを深掘りしたり、過去記事を客観的に振り返ったりすることで、「なんとなく感じていたこと」が言語化される瞬間がありました。
このプロセスこそ、収益が出ていない時期でも“学び”を得る大きなチャンスだと思っています。
自分のブログって「どんな読者に刺さる?」をAIと一緒に棚卸ししてみた
記事が増えてきたものの、収益にはまだ結びつかない。
そんな中でふと、「自分のブログって、どんな人に向けて書いてるんだろう?」という根本に立ち返ってみました。
なんとなく「商品紹介ブログだから、欲しい人に届けばいいよね」と思っていたものの、実際には「誰に届けたいか」が曖昧なままだったんです。
AIに過去記事の傾向を分析してもらうと、想像以上に偏りがあったり、「この切り口で書いた時の反応が良かった」というパターンが可視化されました。
自分では意識していなかったけど、文章のトーンや商品選びに“ある共通点”があったんです。
それをAIと一緒に言語化していくと──
「安くてコスパ重視、だけど“ちょっと人とは違う選び方”をしたい人」
というペルソナが浮かび上がってきました。
この読者像が見えたことで、商品の選定・切り口・タイトル・記事構成すべてが一貫しやすくなり、「この人のために書こう」という軸ができました。
結果として、書く前の迷いや不安も減り、記事作成がスムーズに進むようになった感覚があります。
なぜ売れないのか→売る気がある文章になってなかった
収益ゼロの原因って「アクセスが来ない」と思いがちだけど、実は売る気のない書き方をしていたことに気づきました。
最初は「とりあえず商品の情報を丁寧に書けば、必要な人が買ってくれるはず」と思っていたんです。
けれど、実際に文章を読み返してみると、“誰にどうしてほしいのか”がまったく伝わらない内容だったんですよね。
例えば…
- 「良い商品です」と書いて満足していた(でも、どこがどう良いのか、誰にとって良いのかが曖昧)
- 「今買うべき理由」に触れていなかった(買うタイミングを後押しする材料がなかった)
- 「これが欲しい!」と思わせる文脈を作っていなかった(悩み→解決→行動の流れが弱かった)
要するに、商品の魅力を紹介しているようでいて、読者の行動を促す“導線”が欠けていたということ。
AIに「この文章って売れると思う?」と聞いてみたら、まさに「感情に訴える部分がないですね」とズバッと指摘されて、ドキッとしました(笑)
そこからは、「どんな気持ちの読者がこのページに来て、どう変化して帰っていくのか?」とい“感情の設計”を意識するように。
たとえば、不満・不安・面倒くささ・憧れといった感情に寄り添うことを意識して文章をリライトすると、クリック率や滞在時間にも変化が見えてきました。
「クリックされる記事」って、実はタイトルより●●かも?という仮説
「タイトルが大事!」とよく言われますよね。
たしかに、検索結果で目にする一番の情報がタイトルなので、重要なのは間違いありません。
でも、最近思うのは「アイキャッチ画像の訴求力」の方が、記事のクリックに与える影響が実はかなり大きいのでは?という仮説です。
実際にAIで生成したアイキャッチ画像を、より“悩みを解決するイメージ”に寄せて差し替えたところ、同じ記事のCTR(クリック率)が明らかに上がったんです。
タイトルはそのままでした。
その画像は、ただ商品を写したものではなく、「その商品で得られる理想の未来」を視覚的に表現したものでした。
たとえば「時短家電」の記事なら、ただ家電本体を映すのではなく、“ラクして笑顔で過ごす家族の食卓”のようなイメージ。
特に楽天アフィリの場合、商品名だけでなく「誰のどんな悩みを解決するか?」が視覚で伝わると、反応が全然違うように感じています。
SNSなどで流入を狙う場合も、タイトルより画像が先に目に入るケースが多いため、「画像は読者とのファーストコンタクト」という意識を持つようになりました。
これからは「タイトルと画像はセットで訴求力を最適化する」という考え方が、ますます重要になりそうです。
今後の自分の推しジャンルをAIに相談してみた結果のシェア
「これから何の記事を増やしていこう?」と悩んだ時、AIにこう聞いてみました:
「過去記事の傾向から、伸びしろのあるジャンルを予想してみて」
手元のデータを元に、AIに記事のCTR・CVR・クリック数などを一覧で出してもらうと、思わぬ傾向が浮かび上がってきました。
- カテゴリA:クリックは多いが売上は少ない(情報収集だけして離脱する傾向)
- カテゴリB:アクセスは少ないがCVRが高い(少数精鋭でしっかり買ってくれる)
- カテゴリC:検索ボリュームはあるが、自分の切り口が弱くて目立たない
この中で注目したのが、カテゴリB。 AIからは「購買意欲の高い読者が集まりやすいジャンル。
競合も比較的少ない」と分析が出てきました。
実際にカテゴリBの過去記事を見返すと、読者の悩みに対して具体的な解決策を提示していたり、この商品を買ってこう変わった」というストーリー性が強かったことに気づきました。
そこで今後は、カテゴリBを中心に新しい記事を増やしつつ、カテゴリAやCにはカテゴリBの訴求要素(悩み・共感・ストーリー)を組み込んでテストしてみようと決めました。
こういった戦略的な判断も、数字を元にAIと整理していくと納得感があるし、自信を持って進めるようになります。
自分ひとりで考えてたら気づかなかった視点でした。何より、感覚ではなく“データ×視点”で進められるのが心強いです。
セール以外の時期でも売るには?AIに聞いたオフ期訴求のヒント
セール期以外って、なかなか売上が立ちにくい…。
価格のインパクトが弱くなる時期は、読者の購買意欲も下がりがち。
でも実は、そんな“オフ期”だからこそできる訴求があるのでは?と思い、AIに相談してみたんです。
そこで出てきたヒントがこちら
「価格」より「生活の変化」に寄り添った訴求を。
つまり、「安いから買う」ではなく、「今の暮らしに必要だから選ぶ」という流れを意識するということ。
たとえば
- 新生活・引っ越し準備(春先や9月など、住環境が変わる時期)
- 暑さ・寒さ対策(エアコン、加湿器、冷感寝具など季節系の需要)
- 夏休み・冬休みの家族時間(子どもとの時間を豊かにする便利グッズ)
- 年末年始の準備・片付け(収納・掃除アイテムなど)
こうした「季節ごとの変化」や「生活のイベント」を切り口にして、「このタイミングだからこそ役立つアイテムですよ」という流れを作ってみたところ、セールがない時期でもクリックや購入がしっかり発生しました。
記事の中では「○月に入って○○を感じ始める方も多いですよね」といった“時期を意識した共感ワード”を入れることで、読者の関心を引きやすくなると感じました。
AIからも、「単に商品の良さを紹介するより、“今の読者の状況”に沿った言葉選びのほうが効果的」とアドバイスが。
この視点で記事を書いたら、セールがなくても意外と売れました。
まとめ:収益ゼロ期こそ、思考整理と「気づき発信」
最初は「結果が出ないからこそ、書くことがない」と思っていました。
でも今は、「結果が出ないからこそ、考えたこと・試したことを言語化する」ことが、
未来の収益につながる武器になると感じています。
というのも、この“ゼロ期”にこそ、自分の思考を掘り下げる余白があるからです。
結果が出始めると忙しさや数字に追われて、なかなか内省に時間を使えなくなります。
でもゼロ期には、失敗も含めて「なぜ?」「どうすれば?」と自分に問いかける時間がある。
それを文章に落とし込んでおくと、あとから読み返した時に「これがターニングポイントだったんだな」と気づけるんです。
また、“うまくいっていない”という経験そのものが、これから同じ道を歩く人への貴重な発信材料になります。
「私も同じだった」と言える共感が、人の心を動かす──そう信じています。
同じように伸び悩む時期を経験している方のヒントになれば嬉しいです。
「今はまだ何も成果がない…」と感じる時期こそ、自分だけの思考と試行錯誤を積み上げる大切なフェーズです。
また気づきがあれば、引き続きシェアしていきますね!
それでは、また!