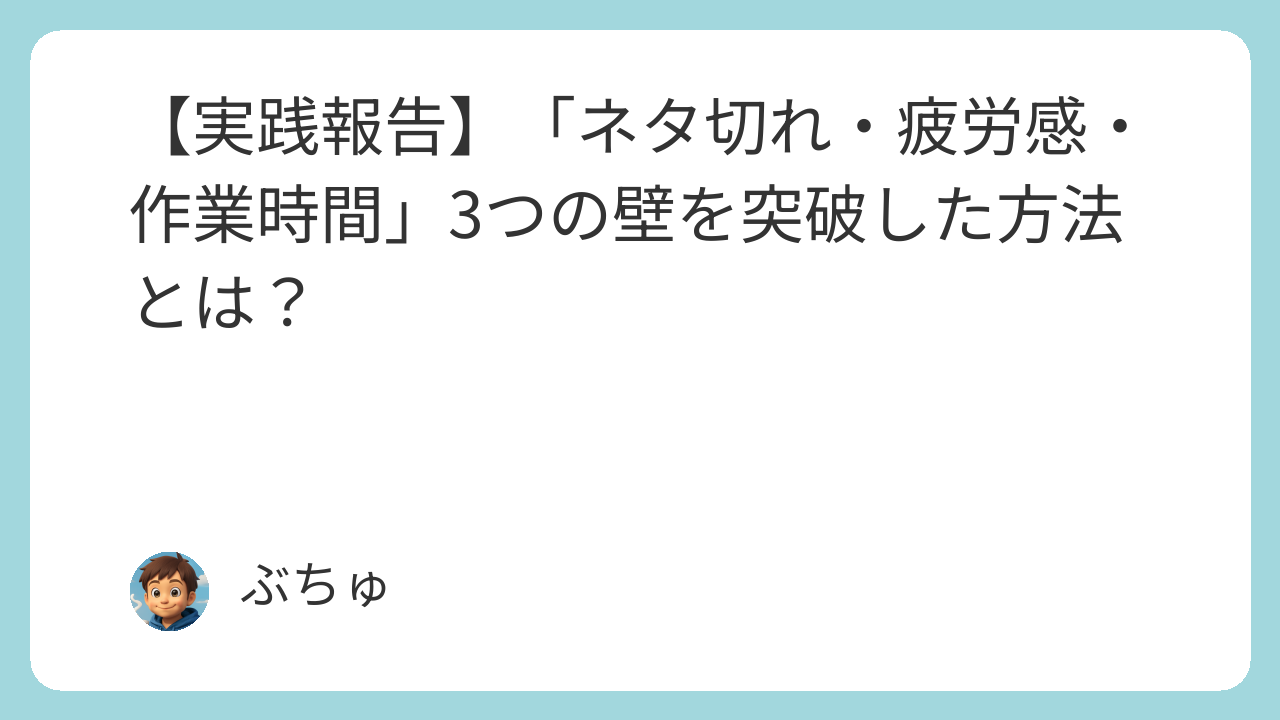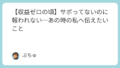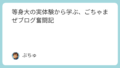こんにちは、ぶちゅです。
今回は、私が実際にごちゃまぜ系アドセンスブログで直面していた 「毎日のネタ探しのストレス」「記事作成の重さ」「伸びないアクセス数」 この“3つの壁”をどう突破したのか―― そのリアルな気づきと、転機となった工夫をお届けします。
◆ AIを使い始めたら疲労感が激減した理由
正直、以前は1記事書くたびにクタクタでした。 ネタを探して、構成を練って、文章を整えて、アイキャッチを作って…。
頭のリソースをフル回転させていたんですね。
特に、何を書けばいいか悩んでいる時間や、文章の語尾や言い回しに迷う時間が長く、それが積もり積もって「なんか今日も疲れたな…」という状態に繋がっていました。
ところが、ChatGPTやCanvaなどのAIツールを活用し始めてから、 「考える作業」の負担がグッと減り、 “気持ち的な疲労”がほとんどなくなったんです。
作業の中で一番エネルギーを使っていた「ゼロから考える」工程をサポートしてくれることで、脳の使用率がぐっと下がった感覚です。
たとえば
- タイトル案 → ChatGPTが10案出してくれる。その中から自分の感覚に合うものを微調整するだけ。
- アイキャッチ → Canvaのテンプレートにキーワードを入れて、色や配置を少し調整するだけで、プロっぽいデザインが完成。
- 本文構成 → 過去の構成をベースに使い回しつつ、足りない部分はChatGPTに「この見出しで300文字くらい書いて」と依頼。
これらを“補助脳”として使うことで、 「全部自分でやらなきゃ」が「必要なところだけ自分で判断すればいい」スタイルに変わりました。
結果として、頭の余力が生まれ、記事執筆後も「まだ別のこともできそう」と感じられるようになりました。
◆ 1記事にかかる時間を3分の1にした方法
以前は、1記事に3時間近くかけていました。
キーワード選定から、構成作成、本文執筆、アイキャッチ制作、公開までのすべてを手動で行っていたため、非常に時間がかかっていたんです。
特に本文を書いている途中で「あれ?この情報の根拠は?」「この書き方で伝わる?」と迷い、何度も手が止まってしまうことが多々ありました。
しかし、現在は平均1時間以内で仕上がることも多くなりました。
その理由は、テンプレ化とAIの組み合わせによる“工程の自動化・半自動化”です。
私が実際にやっている流れは、以下のようになります。
- キーワード選定(事前にリスト化し、月初にまとめて作成)
- 構成テンプレにキーワードを当てはめ、基本の流れを5分以内で完成
- ChatGPTに見出しごとの本文をラフで書かせて、ベース文を瞬時に用意
- 自分で読みやすい日本語に整えながら、必要に応じて具体例や主観を追加
- タイトル・アイキャッチ作成はCanvaテンプレでパターン化し、画像検索不要に
さらに、過去に作った記事テンプレートや構成表をNotionで管理しているため、 「似たようなテーマならこのフォーマットでOK」という再利用の効率化も実現。
加えて、ChatGPTには「この過去記事と同じスタイルで書いて」と指示を出すことで、 文章のトーンや流れも揃いやすくなりました。
最初は「これって手抜き?」と思いました。
でも、手を抜いたのではなく、“考える部分を整理して任せた”という感覚に変わったんです。
結果として「内容も見た目もクオリティが安定」し、時間にも気持ちにも余裕ができるようになりました。
◆ 「今日は何書けば…」をゼロにした習慣とは?
ごちゃまぜブログあるあるの悩みが、「ネタ切れ」ですよね。 日々の投稿を継続しようと思っても、「今日は何を書こう?」「今の流行って何だろう?」と考え始めると、思考が止まってしまうこともしばしば。これは意外とエネルギーを消耗する作業です。
私がやっているのは、 「ネタの種」を日常的にストックする習慣です。
思いついたときにメモしておく。これだけでも「考える時間」を大幅に削減できます。
具体的には
- X(旧Twitter)のトレンドを毎朝見る(特に朝7時〜9時のトレンドは旬)
- 楽天・Amazonランキングを週に1回チェックし、「今売れてる商品」から切り口を探す
- 自分の検索履歴や買った物、家族や友人との雑談の中で出てきた気づきをEvernoteにメモ
- テレビCMやYouTube広告から「今どんな言葉が使われているか」に注目して記録
また、季節性のネタやイベント関連(例えば「梅雨対策」「クリスマス」「新学期」など)も、時期が近づいたタイミングであらかじめリストアップしておくことで、焦らずに記事を準備できます。
さらに、「これは記事になるかも」というテーマを キーワードリストにストックしておけば、 毎朝「何書こう?」と悩むことなく、ToDoリストのようにテーマを選ぶだけで作業に入れます。
この“迷わず着手できる仕組み”ができたことで、記事の更新頻度が安定し、モチベーションの波も穏やかになりました。
◆ アクセスが増えたのは「ライティング」ではなく構造を変えたから
昔は「もっと上手に書かないと…」と文章力ばかり気にしていました。
表現を工夫しすぎたり、語尾を変化させすぎたりして、「うまく書こう」と意識しすぎるあまり、かえって伝わりにくい記事になっていたことが多かったと感じています。
でも、あるとき気づいたんです。 読者は“うまい文章”より、“わかりやすい構造”を求めていると。
なぜなら、検索から訪れるユーザーの多くは「疑問の答え」や「今すぐ知りたい情報」を求めていて、 それに対する答えがスムーズに見つからないとすぐ離脱してしまうからです。
それ以来、私は次のような構造に統一しました。
- 導入文で「誰に、何がどうなる話か」を明確に提示し、読み手の関心を引く
- 見出しで話の流れを整理して、次に読む内容を予告する
- 各パートに箇条書きや段落の余白を活用し、視覚的に読みやすくする
- 最後に「具体的な行動提案やまとめ」を置き、読み終えた後の納得感を作る
さらに、記事によっては「よくある質問(FAQ)」を末尾に置いたり、「読者の疑問に先回りする構成」を意識したりと、 “わかりやすさ”を軸に設計するようになりました。
すると、明らかに滞在時間や直帰率が改善しました。
「この記事、見やすくてわかりやすかったです!」というコメントも届くようになり、 徐々に検索順位も安定して上がっていくという好循環が生まれています。
▼まとめ:自分の“脳と時間”を解放する仕組みを
ごちゃまぜ系ブログは、テーマが幅広いぶん、 「自分で全部考える」と確実に疲弊します。
どんなジャンルにも対応できる柔軟さが魅力な反面、 毎回ゼロから考える必要が出てくるため、 長く続けようとすればするほど「情報収集疲れ」や「決断疲れ」に直面します。
だからこそ、 AIツールやテンプレ、ネタのストック術、構造の最適化など、 **“自分の脳を消耗しない仕組み”**を持つことが大切です。
「考える」「調べる」「決める」この3つを毎回フルでやると、 どうしても消耗します。
そこを仕組み化で軽くするだけでも、 作業のハードルがぐっと下がります。
たとえば、キーワードリストを月初にまとめておくこと、 記事構成のテンプレを3パターンくらい用意しておくこと、 ChatGPTに頼むべき作業をあらかじめ決めておくこと、 このような「手順の自動化」「選択肢の固定化」が、 思った以上にストレスを軽減してくれます。
もし今、「しんどい…」と感じているなら、 それはあなたが「頑張りすぎているサイン」かもしれません。
そして、その状態に気づけた今こそ、 “仕組みを見直すタイミング”なのだと思います。
ぜひ、今日の内容があなたにとっての “小さな突破口”になればうれしいです。
あなたのブログ運営が、よりラクに、楽しく、 そして長く続けられるものになりますように。