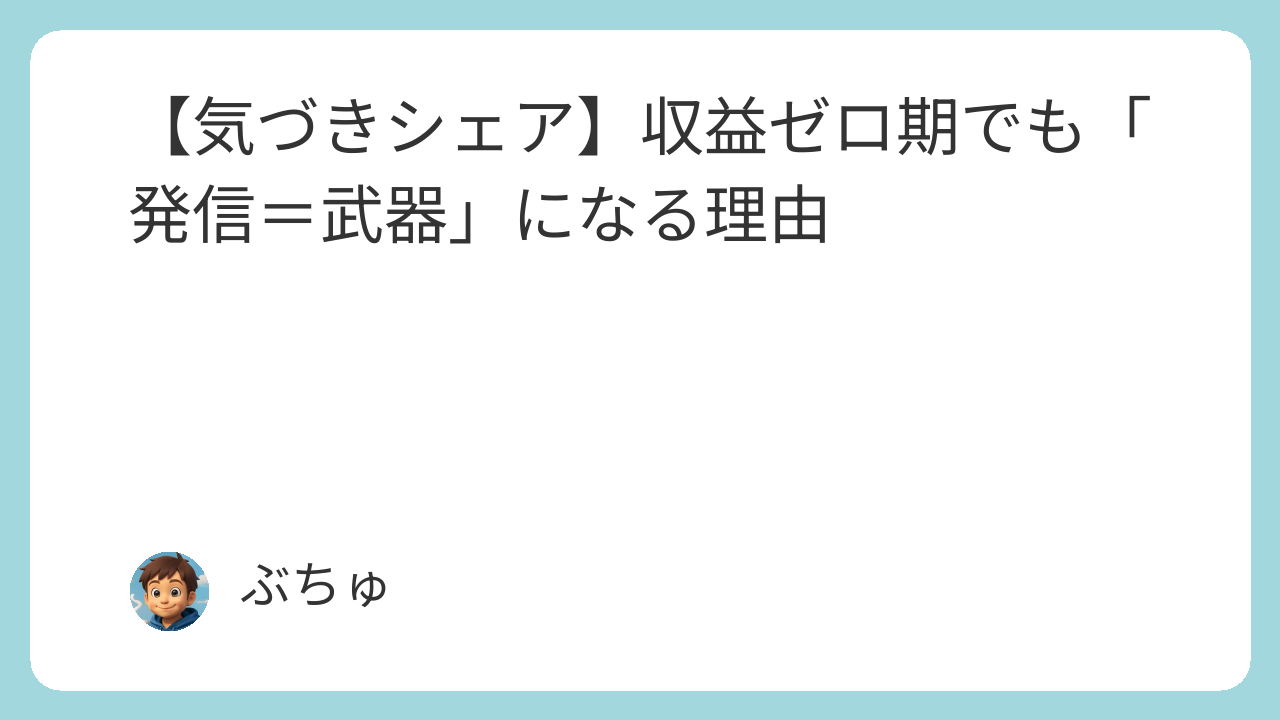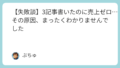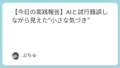こんにちは、ぶちゅです。
今回は、商標系ブログの「収益ゼロ期」にフォーカスして、僕自身が最近AIを活用しながら整理したことや、そこから得た気づきをシェアします。
収益が出ない時期って、つらい。
でも、じつはこの時期こそ「発信の力」がジワジワ効いてくると感じたんです。
■自分のブログって、誰に刺さる?
先日、ChatGPTにこんなふうに聞いてみました。
「自分のブログは、どんな悩みを持つ人に響くと思う?」
すると、商品ジャンルや記事タイトルから、想定される読者像をいくつか提案してくれました。
しかも、それが自分では気づけなかった“リアルな悩み像”にまで踏み込んでいて、ハッとさせられました。
たとえば「家電系レビュー」を書いてる記事なら…
- 初めて家電を買い替える人(説明書が不安な人)
- プレゼントに迷っている人(失敗したくないニーズ)
- 安さより“失敗しない選び方”を重視する人(口コミを読み込んでる層)
- 比較が面倒で、すでに誰かが選んだ“おすすめ”を知りたい人
このように、一見似たようなターゲットでも、実はその背景には「不安」「面倒くささ」「誰かの体験を参考にしたい」など細かな感情があります。
これって、自分が書いていたときには正直あまり見えていなかった視点でした。
記事を書くときって、どうしても「検索キーワード」や「商品スペック」にばかり目が向いてしまいがちですが、その奥にある“人の感情”に意識が向くと、文章のトーンや構成も変わってきます。
「誰に届ける記事なのか」を改めて整理することで、読者が読み進めやすくなる見出しや、納得してクリックしやすい導線の改善点も見えてきます。
これは、ブログ全体の方向性を再確認するうえでもかなり有効だと感じました。
■売れない理由=「売る気がない文章」だった
ある記事を見直していて、ふと気づきました。
売れない理由って、結局「訴求が弱すぎる」ことだったんです。
たとえば、商品の魅力をスペックや特徴で説明しているだけでは、読者の“感情”には届かない。
レビュー自体はしっかり書いているつもりでも、「この商品が、どんな悩みを抱えている人に、どんなふうに役立つのか」が伝わっていなかったんですね。
読者が「自分に関係あるかも」と思えない限り、次のアクションにはつながりません。
読者の背中を押す言葉って、意識していないと全然出てこない。たとえば、「これを選んだことで、○○の不安がなくなった」「実際に使ってみて、△△の手間が激減した」みたいな“具体的な変化”を伝えるだけでも、説得力は一気に上がります。
ここでもAIが活躍しました。
「この文章、買う気になる?」とChatGPTに聞いたら、驚くほど冷静にダメ出しをしてくれて(笑)、淡々とした文章のどこが説得力に欠けるかを的確に指摘してくれました。
たとえば、「“おすすめです”と書いてるけど、なぜそう思ったのか具体的に書かれていない」「読者が共感しそうな体験談が欠けている」といった点。
そのフィードバックをもとに、文章を修正していくと、自然と読者視点の文章に近づいていく実感がありました。
AIとの対話を通じて、「書き手の熱量」や「読者への想像力」が、売れる文章のカギなんだなと改めて実感しました。
■「クリックされる記事」って、タイトルよりも実は●●?
タイトル改善ばかり気にしていた僕ですが、最近ある仮説が浮かびました。
記事がクリックされるかどうかは、「ブログ全体の雰囲気」が大きいのでは?
というのも、似たようなタイトルでも、
✅ 書き手の視点が感じられる記事
✅ 他の記事も“なんか読みたくなる”空気感のブログ
は、クリックも滞在時間も明らかに長くなる実感がありました。
たとえば、レビュー記事で「この製品のここが便利!」と書かれているだけではあまり印象に残らないのに、 「自分はこういうシーンでこの商品を使っていて、他と比べてこう感じた」というストーリーが入っているだけで、グッと引き込まれるんですよね。
また、記事一覧をざっと見たときに、「このブログはちゃんと調べて書いていそうだな」とか「読みやすそう」といった印象があるだけで、つい他の記事も見てしまう。
それが結果的に、1記事のクリック率だけでなく、サイト全体の回遊にもつながる。
そう考えると、“空気感”というのは、1つの記事の中身だけでなく、複数記事の並びやカテゴリ構成、文体の一貫性など、全体設計にも関係しているんだと思います。
その“空気感”を作るには、やっぱり「どんな視点で記事を書くか」「読者との距離感」が大事なんですよね。
読者に寄り添っている感じを出す、ちょっとした言葉のトーンや表現の柔らかさが、案外大きな違いを生む。
ここもAIにフィードバックもらいながら調整中です。記事ごとに「全体としてどんな印象を与えているか?」をChatGPTに聞いてみると、第三者視点の気づきが得られて、すごく助かっています。
■今後の“推しジャンル”をAIに相談してみたら…
このままでいいのか?と迷っていたとき、ChatGPTにこんな相談をしました。
「今の自分のブログ内容や実績から、相性が良さそうなジャンルって何?」
この質問に対して、AIは意外にも具体的かつ多角的な視点からアドバイスをくれました。
まず、過去の記事内容をベースに「どのジャンルが多く書かれていて、どのタイミングで反応があったか」などを踏まえ、ブログ全体の傾向を分析。
それに加えて、一般的な市場動向も踏まえたうえで、以下のようなジャンルを提案してきたんです。
- 季節変動が少なく、年間通して安定した需要があるジャンル(例:収納用品、日用品、健康関連)
- 訴求に体験談が活かせるジャンル(例:使ってみて生活がどう変わったか伝えやすいもの)
- レビュー重視の比較系ジャンル(例:複数商品の違いを丁寧に伝える構成が向いているもの)
さらに面白かったのが、「書き手の性格や強み」と「そのジャンルとの相性」まで言及してくれたこと。
たとえば、「じっくり調べて比較するのが得意な人は、スペック差を可視化できる家電・文房具系が合いやすい」とか、「実体験を語るのが自然にできる人は、美容・ライフスタイル系で力を発揮しやすい」など。
単に“売れそう”ではなく、“自分にとって継続しやすいジャンル”という視点がとても参考になりました。
“なるほど!”と思いつつ、自分が苦手意識を持って避けてたジャンルも、こうして整理してもらうと「意外といけるかも」と思えてきたのが大きな発見でした。
実際、今はその中から1つをピックアップして、トライアル的に記事を作っているところです。
AIに聞くことで、「自分では選ばなかったかもしれない道」に光が当たる感覚がありますね。
■セール以外でも売るには?AIに聞いたオフ期訴求のヒント
最後に、これも最近の気づきです。
セール時期以外って、どうしても購買意欲が低くなりがちで、なかなか成果が出にくいですよね。
アクセスはあるのに売れない。クリックされてもカートに入らない。そんな“空振り”の感覚を何度も味わってきました。
そこで、ChatGPTに「セール期以外でもクリック率や成約率を上げるにはどうしたらいいか?」と聞いてみたんです。
すると、AIから返ってきたのは、売り込み感を出さずに“納得してもらう”ための3つのヒントでした。
- 「急がないけど、いずれ買う」層に刺さる言葉を入れる
→ たとえば「これから買い替えるなら候補に入れておきたい○○」や「買う前に知っておきたいチェックポイント」など、今すぐ買う気はなくても“保存”されるような切り口。 - 「先回り購入のメリット(在庫切れ防止、ポイント還元など)」を打ち出す
→ 「季節前に買うと在庫が選べる」「今なら○○ポイント還元対象」など、行動の後押しになる“理由”を提示。 - 「後悔したくない人向け」の視点で比較記事を作る
→ 「買って後悔しないために見るべき○つのポイント」「迷ったときの選び方」など、損したくない心理を刺激する構成。
このように、セール期の“お得感”ではなく、「納得感」「不安の払拭」「タイミングの提案」によって、オフ期でも購買を後押しすることができるという視点が新鮮でした。
たとえば最近、ある季節家電の比較記事を「在庫切れになる前に買っておくべき理由」という切り口でリライトしたところ、CTRと滞在時間が大幅に改善しました。
クリックされるのはもちろん、「今のうちにチェックしておこう」という行動につながっている感触があります。
…こういう「淡々と検索している人にそっと背中を押す」訴求って、つい忘れがちですが、実は成果に直結するんだと改めて感じました。
AIに相談すると、自分では思いつかない“タイミング視点”や“読者の心理変化”を指摘してくれるので、こういったオフ期施策にもどんどん活用していきたいと考えています。
まとめ:発信は、思考を深める“練習”でもある
収益が出ない時期は、「向いてないのかも」と思ってしまうこともあります。
でも、思考を整理して、それを発信に落とし込んでいくことで、
✅ 記事の精度が上がる
✅ 読者像がクリアになる
✅ 売れない理由の“正体”が見える
など、ちゃんと前に進めると感じています。
もし同じように迷っている方がいたら、まずは「思考と実践の棚卸し」からやってみてください。
そして、気づきをぜひ発信してみてくださいね。発信こそ、ブログ力の原点かもしれません。