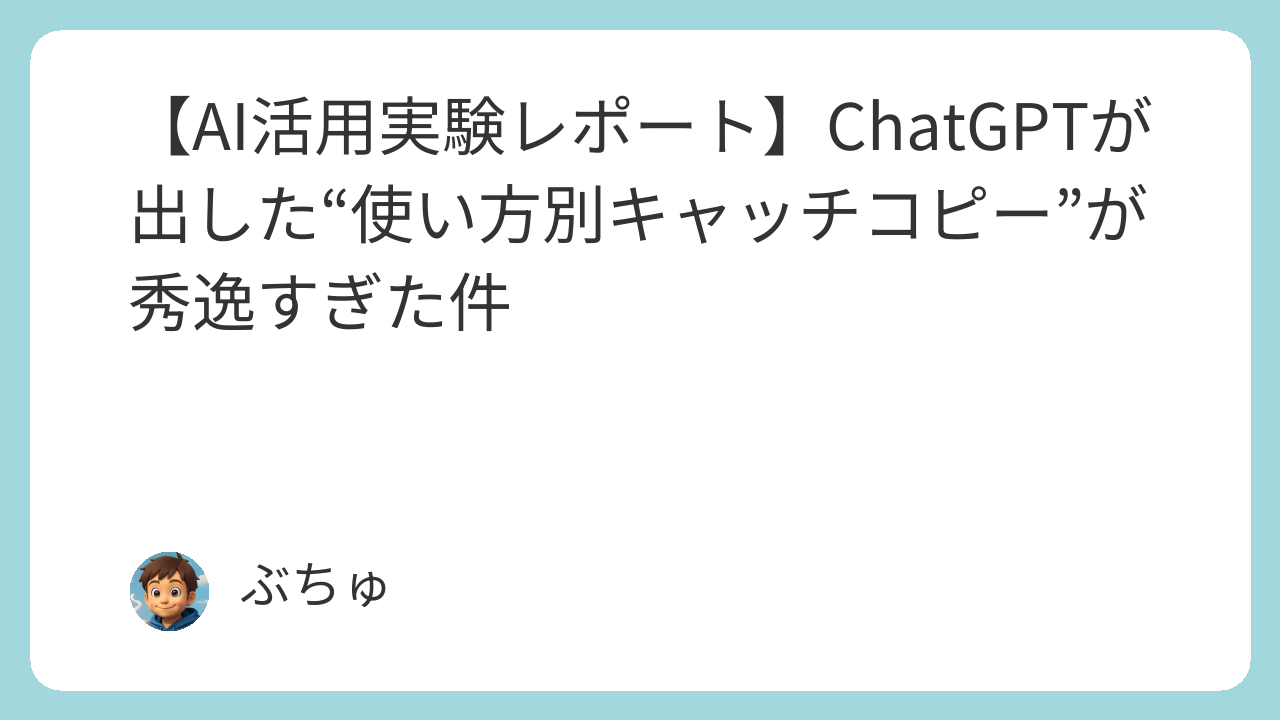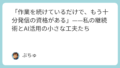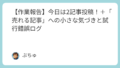こんにちは、ぶちゅです。
今回は、僕が最近個人的に取り組んでみた**「ChatGPTにキャッチコピーを考えさせる実験」**について、実際のやり取りや気づきを交えて詳しくシェアしてみようと思います。
この実験は、記事づくりの新しい切り口を探している中で思いついたもので、「AIにどこまで任せられるのか?」「実際に読者の心に刺さるコピーを作れるのか?」という点を自分なりに検証することが目的でした。
◆実験内容:
あるキッチン家電を紹介する記事を作っていた時のことです。
その商品は、特に「どう使うか」で価値が分かれるもので、使う人のライフスタイルによって魅力が変わるタイプの製品でした。
記事の冒頭にキャッチコピーを入れたいと考えていたのですが、どんな切り口がいいか悩んでいました。
そんなとき、「使い方ごとに異なる切り口をAIに出させたらどうなるだろう?」というアイデアが浮かび、試しにChatGPTにお願いしてみることにしたんです。
具体的には、使う人のシーンをいくつか想定して、そのパターンごとに刺さるキャッチコピーを考えてもらうという形でプロンプトを作成。
すると、想像以上に的確で刺さる案が次々と返ってきて、正直驚かされました。
「〇〇(商品名)を使う人の使い方タイプ別に、それぞれの心に刺さるキャッチコピーを考えて」
この一文だけでも、ChatGPTは読者像や使用シーンを想定した上で、見事にバリエーション豊かな提案をしてくれたんです。
◆出てきた案がこちら(一部抜粋):
ChatGPTが提案してくれたキャッチコピーの中から、特に「使う人の背景」がにじむような、読者の共感を誘いやすいフレーズをピックアップしてみました。
- 忙しいママ向け:「朝の10分が自由時間に変わる、魔法のキッチン家電」 → 子育てや家事に追われる毎日の中で、“朝の余裕”という価値を提示してくれる文言。想像以上にピンポイントな悩みに刺さります。
- 一人暮らしの男性向け:「料理しない僕が、自炊を始めた理由」 → 「自炊はしないもの」という先入観を覆すフレーズで、興味を引きつけながら、商品への入り口を自然に作ってくれています。
- 料理好き主婦向け:「“あと1品”を手間ゼロで。平日ごはんがもっと楽しく」 → 料理の楽しさと面倒さの間にいる主婦層に、“楽になるのに満足度が上がる”というメリットを提案しています。
この3つだけでも、単なるスペック説明とは全く違う角度からのアプローチになっているのが分かります。
……これ、普通にそのまま使えるレベルじゃないですか?笑
実際に記事の構成やタイトル案にも応用してみたところ、読者の滞在時間が伸びたという結果も出ています(また別の機会に共有します)。
◆気づきとポイント
僕たちアフィリエイターが「つい書きがち」なのは、商品のスペックや機能、価格などを整理して、
誰にでも通用するような“万人向け”のコピーです。
「この商品は便利ですよ」「時短になりますよ」「多機能です」——確かに伝えたい要素ではあるのですが、それだけでは読者の心を動かすのは難しいんですよね。
でも実際、読者が心を動かされてクリックしたり、読み進めたりするのは、**「これは私のための商品かも」「まさに今の自分にぴったり」と感じさせる“パーソナルなコピー”**なんです。
たとえば、「平日、子どものお弁当作りに追われているあなたへ」や、「料理は苦手。
でも外食は減らしたいあなたへ」のような、読者の“状況”や“悩み”に寄り添った一言があるだけで、反応がまったく変わってきます。
こうしたコピーを考えるためには、読者のペルソナを何パターンか用意して、それぞれに刺さる言葉を探す必要があります。でも、手動でやると時間もかかるし、発想も限界がある。
そこで役立つのがChatGPTです。
想定読者ごとに切り口を分けてプロンプトを出せば、それぞれに合った訴求ポイントやキャッチコピーを、一気に洗い出すことができるんです。
これは、単なる効率化ではなく、視点を増やす意味でも非常に有効だと実感しました。
◆活用のススメ
ChatGPTで生まれた使い方別キャッチコピーは、単に見出しや導入文だけでなく、記事のあらゆる部分で活かせるのが魅力です。
たとえば、記事タイトルに応用すればクリック率アップに直結しますし、リード文に組み込めば“この記事は自分のための情報だ”と感じてもらいやすくなります。
さらに、アイキャッチ画像のテキストとしても非常に効果的です。
画像とキャッチの整合性が取れているだけで、読者の目に留まりやすくなり、記事の第一印象がグッと良くなります。
応用のコツとしては、**「誰に向けて」「どんな場面で使うと」「どう嬉しいか」**という3点を分解し、それぞれに対してChatGPTに問いかけてみること。
一度テンプレート化しておくと、他の商品記事にもスムーズに応用できます。
興味のある方はぜひ、次回の記事制作で“使い方別キャッチコピー”実験を取り入れてみてください!
単なる発想支援にとどまらず、記事の設計そのものをアップグレードできる実感が得られるはずです。