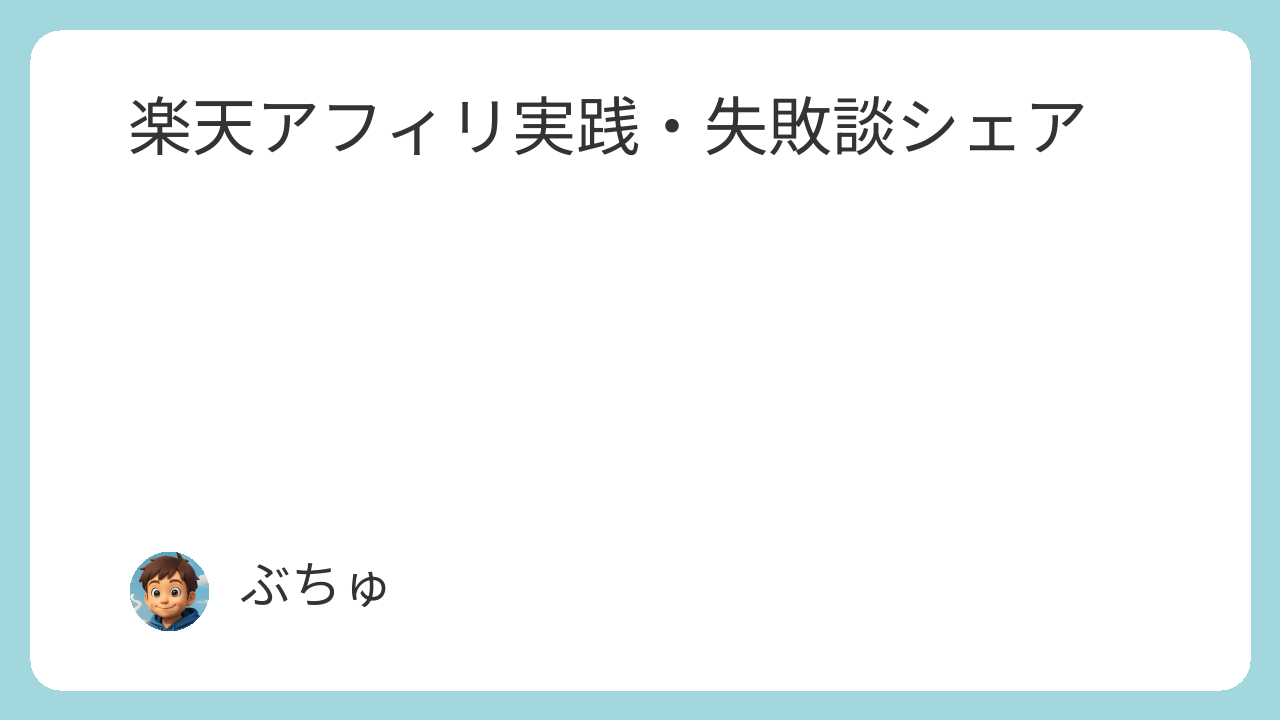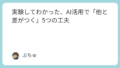こんにちは、ぶちゅです。
今日はちょっと恥ずかしい、でも「誰にでもあること」と思ってシェアする話です。
実際に体験したときは、かなり落ち込みましたし、「自分だけがうまくいっていないのでは?」と不安にもなりました。でも、同じような経験をしている人も多いと気づいてからは、むしろ「これは共有したほうが意味があるかもしれない」と感じるようになりました。
うまくいかない日があるのも、遠回りすることがあるのも、アフィリエイトの現場では当たり前。だからこそ、「あなただけじゃない」という視点で、今日は赤裸々にいろんな失敗談を綴ってみます。
3記事書いたのに売上ゼロ…「原因が全くわからなかった」日の話
先日、「これはいける!」と思った商品を3つ選んで、朝から集中して記事を書き上げました。
・レビューあり ・価格帯もほどよく ・検索ボリュームもそこそこ
ライバルと比較しても、紹介の切り口に工夫したつもりだったし、画像選びも丁寧にやりました。「今回はいける!」と手応えがあっただけに、モチベーションも高く、執筆も集中できました。
「完璧じゃん」と思っていたのに、結果は…クリックすらほぼゼロ。
「え?」とPCの前で固まりました。1時間後、アクセス解析を見ても動きなし。まるで誰にも存在を気づかれていないような感覚。
リライトしても変わらず、何が悪いのか、心当たりがない。焦りとモヤモヤが混ざって、「自分の書き方が根本的にズレているんじゃないか?」とさえ思いました。これ、地味に一番しんどいです。
でも、気持ちを切り替えて、冷静になってChatGPTに相談してみました。すると返ってきたのが、
→「この商品、競合が多すぎてあなたの記事が埋もれてますよ」 →「タイトルが一般的すぎて目に止まってない可能性あり」
…たしかに。
検索してみたら、同じ商品を紹介している記事がずらっと並んでいて、その中に自分の記事が埋もれているのを実感。
タイトルも、無難にまとめすぎていて、“読む理由”が伝わっていなかったかもしれません。
やっぱり主観だけだと“ズレ”に気づけないんだと痛感しました。 今では記事を書くたび、「これ、検索結果に埋もれてないか?」「タイトルは目に止まるか?」をChatGPTと一緒にチェックするようにしています。
商品説明が丸パクリっぽくなってて凹んだ。でもAIが別角度を提案してくれた
楽天の商品ページを見て、そのまま説明文を書いてしまったことがあって。 最初は「この商品ってどんな機能があるんだろう」と調べるためのつもりで読んでいたのに、 気づけば公式の説明文をベースに、ほぼそのままの構成で自分の文章を書いてしまっていました。
あとで読み返すと「これ、ほぼ公式そのままじゃん」と凹みました。 しかも、読み物というより“商品情報のコピペ”みたいな印象で、 「これじゃ検索で上位に行くはずないよな…」とがっくり。
「自分の言葉で伝えるって、意外と難しいな」と悩んでいたとき、 ふと思いついて、AIに「この商品のメリットを“子育て中のママ向け”に言い換えて」と投げてみました。
→「朝のドタバタ時間に1分でも時短になるなら…と考えてるママに」
という返答が返ってきて、思わず「それだよそれ!」と声が出ました。
商品のスペックをそのまま書くんじゃなくて、 “どんな人が、どんなシーンで、どんな気持ちで”使うのか。 そこを意識するだけで、文章がぐっと“人に向けた”ものになるんですよね。
AIの提案をベースに、自分の体験や身近な人のエピソードも交えて書き直したら、 同じ商品なのにまったく違う印象の記事になって、「やっと伝わる気がする」と感じられました。
「伝える」と「書く」は違うんだなあと実感した瞬間でした。 そして、AIは“正解を出す道具”というよりも、“視点を変えるパートナー”なんだな、とも。
セール直前に焦って量産→結局ほぼクリックなし。その理由を分析してみた
楽天セール直前、「今のうちに仕込まないと!」と焦って記事を6本書きました。
この時期はアクセスが伸びやすいし、購買意欲も高まるタイミング。そう思って「とにかく数を!」と手を動かし続けたのですが、
でも蓋を開けてみると、クリックもごくわずか。売上は当然ゼロに近く、「あんなに頑張ったのに…」という虚しさだけが残りました。
あとで冷静に見返すと、いろんな“見落とし”がありました。
・タイトルに「今買う理由」が書かれてない → セール前なのに緊急感ゼロ ・商品選びが「売れてるから」だけで浅かった → ユーザーの“欲しい理由”が見えてなかった ・季節感や悩みに寄り添えてなかった → ただの商品紹介で終わっていた
どれも致命的でした。
焦って書いた記事ほど、見返すと“誰にも届かない内容”になっていることに気づかされます。 自分の中で「投稿した」という満足感だけが残っていて、読み手の存在が完全に抜け落ちていました。
逆に、「焦らず1記事だけ丁寧に書いたやつ」はちゃんと成果が出ていたりします。 その記事では、ユーザーの悩みを先に想像し、検索意図を掘り下げ、画像や導入文もじっくり考えて作りました。
結果、クリックも多く、成約にもつながりました。
以来、AIにも「なぜこの商品?誰に?なぜ今?」を毎回問いかける癖をつけました。
たとえば「この商品を選ぶ人の背景」「季節・生活・タイミングとの接点」などをAIに質問して、 自分の思い込みをリセットするようにしています。
数を打つのも戦略の一つですが、「届けたい人の顔が見える記事」が、やっぱり最後は強いんだと痛感した経験です。
「売れる商品は競合が強すぎる問題」をAIと相談したら一筋の光が見えた話
アクセスが集まる=ライバルも多い。
だから売れてる商品を狙っても、「上位10サイトの壁」が厚すぎる。 検索上位には企業系サイトや老舗アフィリエイターのドメインパワーが並んでいて、自分のような個人ブログはなかなか太刀打ちできない…と何度も感じてきました。
そこで、どうにか“違う切り口”で戦えないかと思い、AIに相談してみました。 「この商品の“ズラした切り口”を考えて」と投げてみたところ、すぐにいくつかの提案が返ってきました。
→「この商品を“プレゼント用途”で提案すると検索意図が変わる」 →「“使い方が限定される場面”に寄せるとライバルが減る」 →「ターゲットの年齢層を思いきってずらすことで、新しい切り口が生まれるかも」
このとき、「商品そのもの」ではなく「誰が・どう使うか」にフォーカスすることで、競合の少ない領域を見つけられるという視点が新鮮でした。
たとえば、同じ加湿器でも「赤ちゃんのいる家庭向け」「一人暮らしの狭い部屋向け」「冬場の声優さんの喉ケア用」など、用途を掘るだけで切り口がガラッと変わります。
さらに、AIに「その切り口に合わせたタイトル案も10個ください」と追加でお願いすれば、量産された一般的なタイトルとの差別化にもつながります。
など、王道を少し横から攻める視点が出てきて、「これなら自分でもいけるかも」と希望が持てました。
今では、競合が多いとわかった時点で「真っ向勝負は避けてズラす」→「AIに相談して切り口を探る」→「ターゲット像を具体的に設定する」という流れをルーチンにしています。
タイトルが弱かった…と後で気づいた。AIに強い言葉を相談しとけばよかった
記事公開してしばらく経ってから、たまたまリサーチ中に自分の記事を見つけたんです。
…が、タイトルがめちゃくちゃ地味。
そのときは「よくあるレビュー記事のひとつ」くらいにしか見えなくて、自分が書いたと気づくのに数秒かかったほどです。
「これ、クリックしたくなるか?」と自問して凹みました。 検索画面では、強い言葉や数字、ベネフィットが並んでいて、比較される前にスルーされるような印象だったんです。
そのとき思ったのが、
→「最初にChatGPTに“強めのタイトル案”を10個出してもらえばよかった」
ということ。
しかも、ただタイトルを出すだけじゃなくて、 「この商品を30代ママ向けに訴求したタイトルを」「この商品の“損したくない”心理に刺さる言い回しを」など、具体的に指示することで、AIは想像以上に鋭いコピーを出してくれることもあります。
さらに、複数案を出してもらうことで、「これはちょっとやりすぎかも」「これは読みやすい」と、自分の中での“言葉の温度感”を測る指標にもなるんですよね。
AIに頼るのって“手抜き”じゃなくて、“見落としの防止”なんだなと学びました。 むしろ「冷静な第三者の視点」を持ち込むことができる貴重なプロセスだと、今では思っています。
どれも「やらかした…」と思った瞬間ばかりですが、 この失敗を次に活かせれば、すべてが“前進の材料”になります。
「あなただけじゃない」、これを伝えたくて今日は書きました。
では、また次回!