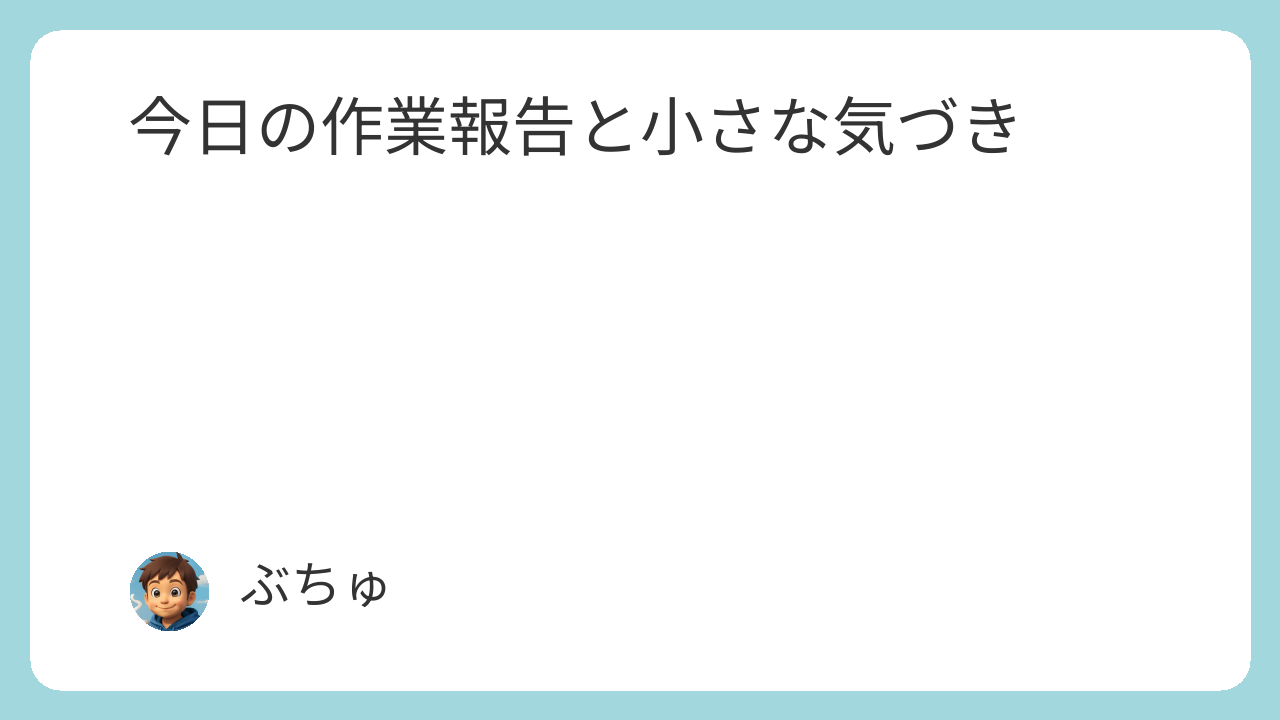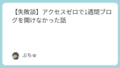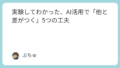こんにちは、ぶちゅです。
今日は、自分の取り組みの中で感じたことや、ちょっとした工夫、そして試してみて得られた“気づき”について、少し詳しくシェアさせてください。
どれも些細なことかもしれませんが、日々の積み重ねや気づきを言語化して残しておくことで、自分自身の学びにもなりますし、同じように取り組んでいる方の参考になれば嬉しいです。
今日やったこと
- 2記事投稿しました。どちらもChatGPTに見出し構成を提案してもらいました。見出しの粒度や順番、ユーザー目線で気になるポイントなど、AIの視点はやはり新鮮で、「こういう切り口もあったのか」と発見も多かったです。
- 特に、1記事目は「この商品、売れそう!」という直感をもとに着手。ChatGPTにタイトル案を5パターン出してもらい、A/Bテスト的にどれがクリック率に影響するのかをチェック中です。本文の導入文にも少しバリエーションをつけてみたので、タイトル×導入の掛け合わせによる変化も見ていこうと思います。
学び1:レビューが少ない商品でも「書く価値アリ」
今日は、楽天レビューが少ない商品でもあえて記事にしてみました。
こういう商品って、最初は「情報が少なすぎて難しいかも…」「ユーザーの信頼が得られにくいかも」と思いがちなんですが、だからこそ逆に書く意味があるのでは?と思い直しました。
まず、ChatGPTに相談してみたところ、
- どんな悩みを持つ人に響きそうか
- どういう比較軸で紹介すると信頼性が出るか
といった切り口をいくつも出してくれました。単に「良さそうです」と書くのではなく、「この商品を求めている人の背景」や「他と比べてどんな点がユニークか」を明確にするだけで、レビューの少なさをカバーできる記事になると実感。
また、レビューが少ない商品は競合も記事数も少なく、検索結果で上位表示されやすいという利点もあります。つまり、リスクはあるけどチャンスも大きいということ。今後はこういった“未開拓ゾーン”を狙った記事も、積極的に入れていこうと思っています。
「レビューが少ない=書けない」ではなく、むしろ競合が少ないチャンスかも。
そう思えるようになったのは、大きな前進でした。自分の中の「書ける条件」の幅が広がった気がします。今後もこういう小さな挑戦を積み重ねていきたいです。
学び2:「価格帯を変える」と切り口がガラッと変わる
同じカテゴリでも、AIに「もう少し高価格帯の商品は?」と聞いてみたところ、
それまでとは全く異なるジャンルの商品や、別の層に向けた提案がいくつも出てきました。
具体的には、低価格帯では「コスパ」や「手軽さ」が軸になっていたのに対し、高価格帯になると「品質」や「所有感」「長期的な満足度」といった視点が増えてくるんですよね。
この変化に気づいたことで、「同じカテゴリーでも価格帯が変わると訴求ポイントも変わる」ということを実感しました。
そこで思い切って、価格帯の違う2商品を並べた比較記事を作ってみたところ、記事の厚みや読み応えが格段にアップ。読者の「どっちが自分に合うかな?」という迷いを後押しできる内容になりました。
さらに、比較構成にすることで検索キーワードも広がり、「商品A 比較」「商品B 違い」など、複数のニーズを拾えるようになったのも大きな発見。
これは今後のネタ出しや構成においても、非常に使える視点だと感じました。ひとつのカテゴリ内で価格軸を変えるだけでも、まだまだ切り口は眠っていそうです。
今日の気づき:「アクセス=売上」じゃない
今日は、アクセスが多かった記事と、実際に売れた商品を見比べてみました。
アクセス数が多い記事って、どうしても「成果につながりそう」「これが主力になるかも」と期待してしまいがちですよね。私もつい、日別PVランキングを見てはワクワクしてしまうタイプです。
…結果、一番アクセスを集めた記事からは1件も売れていないという事実が判明。Google Search Consoleでも上位表示されていて、クリックも安定していたのですが、肝心の商品リンクのクリック率・成約率はほぼゼロ。まさに「アクセスの質」が問われる展開でした。
一方で、検索ボリュームが少なく、競合も少ないような“ニッチな悩み系キーワード”の記事から、1件の売上が発生していたのを確認。記事のPVは一桁でしたが、明らかに「買う気がある人」が流入してきていたことがデータからも伝わってきました。
つまり、
「アクセスを集める記事」=「売れる記事」ではない
この事実は頭では理解していたつもりでしたが、自分のブログで実データとして確認したことで、その重みやリアリティが一気に増しました。今後は単純なアクセス数に一喜一憂せず、「読者の目的」と「導線の質」を意識していきたいです。
まとめ
今日の作業の中で改めて感じたのは、
「小さな実験」と「地道な観察」こそが、次の一手につながるということです。
派手な成果やバズる記事がなくても、「今日はこれを試してみた」「このパターンではどうなるか?」というような実験と、そこから得られる反応を丁寧に観察することが、積み上げ式で力になっていくのを少しずつ実感しています。
まだ目に見える大きな成果が出たわけではありませんが、こうした“気づきの累積”を言語化して共有していくことで、自分自身の考えも整理されますし、読者の皆さんにとっても何かしらのヒントや共感を提供できるのではと思っています。
メルマガという場所を通じて、自分だけでは気づけなかったことにも気づけたり、思考を深められたりしているのを感じる今日この頃です。
明日も一緒に、一歩ずつ、着実に前に進んでいきましょう。