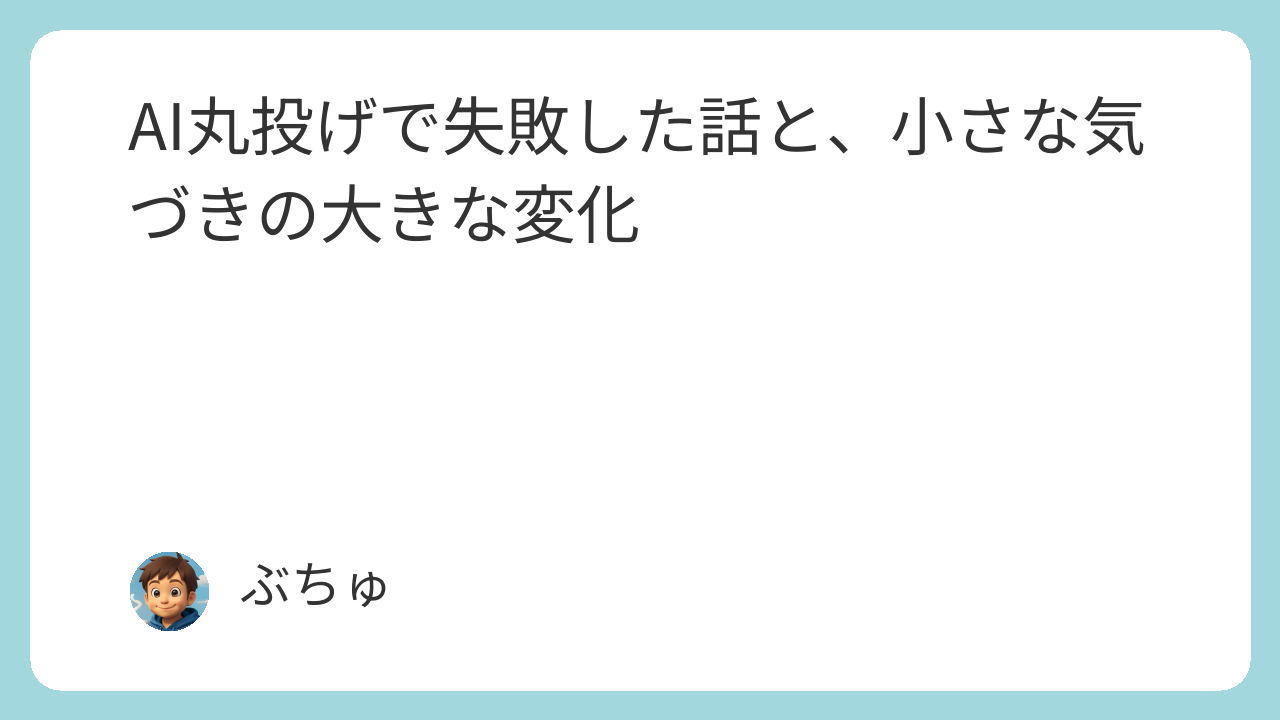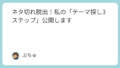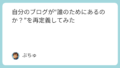こんにちは、ぶちゅです。
今回は「ちょっと恥ずかしいけど、だからこそ価値がある話」をお届けしようと思います。
それは、私自身がアドセンスブログを運営する中で直面したリアルな“失敗”や“つまずき”の記録です。
この経験を正直に綴ることで、もしあなたが似たような壁にぶつかっていたら「自分だけじゃない」と思ってもらえるかもしれませんし、再び手を動かすきっかけになるかもしれません。
「誰にも見せたくなかったアクセスゼロの日々」「AIに丸投げして読みづらくなった記事」「ネタがないと嘆いていた裏にあった本当の理由」…。
今回はそんな実践から学んだ“気づき”や“修正のヒント”も含めて、等身大でお届けしていきます。
■ アクセスがゼロ続きで、ブログを1週間開けませんでした
ブログのアクセス数って、ほんとにメンタルにきますよね…。
私は以前、「数字はただの指標」と頭ではわかっていても、心ではそれを受け止めきれていませんでした。
ある週、公開した記事がことごとく反応ゼロ。
検索流入もSNSからも動きなし。
Google Search Consoleを開いてもインデックスされてないし、アナリティクスを見てもPVはゼロ。
気づけば、アクセス解析を見るのが怖くなってしまって、1週間もブログを開けませんでした。
「せっかく時間をかけて書いたのに誰にも読まれない」
「もしかしてキーワード選定が根本的に間違ってたのかも…」
「そもそもこのジャンル、ニーズなかったんじゃ…」
「こんな調子じゃ、この先ずっと成果出ないかも…」
気づけば、書くのが怖くなっていました。
ネタはあっても、手が動かない。
いつもなら気軽に開けるはずのWordPressの管理画面も、なんとなく避けてしまうように。
そんな負のループに、ずぶずぶとはまっていきました。
1日、また1日と何もしない時間が続いて、気持ちもどんどん沈んでいったんです。
でも、そんな自分を客観的に見て「この状態は自分だけじゃないはず」と思えたことで、ようやく抜け出す一歩を踏み出せました。
■ AIに丸投げして失敗。読み返して自分で反省しました
その頃、記事の下書きをAIに頼りすぎていたことも原因のひとつでした。
毎日書き続けることが重要だと考え、効率重視で記事を量産しようとした結果、AIへの依存度が高くなっていたんです。
見出しだけ決めて、本文はAIにお任せ。
整った構成、きれいな言い回し、情報としては間違っていない。
でも読み返してみると、どこか他人事のようで、スカスカな印象を受けました。
「自分の体験」や「考え」がぜんぜん入っていないから、読み手にとっても“どこにでもある文章”だったんだと思います。
何より、自分自身がその記事に納得できていなかった。
記事の最後に「これでいいのかな…」という気持ちが残るのは、結局“自分が本当に言いたいこと”を書いていなかったから。
そんな状態では、読者に響くわけがないし、自分自身もブログを続ける意味を見失いかけていました。
そこに気づいてから、AIの使い方をちょっと変えました。
まず、骨組みや情報整理にはAIを活用しつつも、具体的なエピソードや想いの部分は必ず自分の言葉で書くようにしました。
また、AIからの提案をただ採用するのではなく、「自分だったらどう感じるか?」「読者にとってどう役立つか?」という視点で必ず見直すようになりました。
「自分の視点を足す」「文章の芯を自分で書く」
この2つを意識するだけで、記事に熱が戻ってきました。
読み手からの反応も少しずつ出るようになり、「自分の言葉が届いた」と感じられる瞬間が増えました。
結果として、書くこと自体がまた楽しくなってきたんです。
効率よりも“納得感”を重視するようになったことで、モチベーションも持続しやすくなりました。
失敗をきっかけに見直したAIとの付き合い方は、今では私のブログ運営に欠かせないバランスになっています。
■ 手が止まる理由は「自分の中にあった」
やらなきゃ、と思ってるのに、なぜか手が止まる…。
頭では「書かないと進まない」とわかっているのに、どうしても気持ちが乗らない。
そんな時期が、しばらく続きました。
「時間がないから」「ネタがないから」なんて言い訳をしてたんですが、実は心の奥に「どうせまた読まれないんじゃないか」という不安があって、それが無意識のうちに手を止めさせていたんです。
前回の記事が読まれなかったというショックが、じわじわと心に残り続けていたんですよね。
“失敗を自分の価値に結びつけちゃってた”んですよね。
アクセスが少なかった=自分の価値がない、みたいに極端な思考になっていたことに、あとから気づきました。
でも、アクセスがゼロでも「書いたこと自体」は成長だったし、書いたことで「今の自分には何が足りなかったか」が見えてきた。
そしてなにより、感情が動いた出来事を言語化して書き残しておくことが、次の行動につながる“地ならし”になるんだと、ようやく理解できました。
気づきを得たことで、今こうしてメルマガを書けていますし、「書くことで回復していく自分」を実感できたのは、本当に大きな収穫でした。
■ 用語の理解もAIが助けてくれた
あと、自分がつまずいてたのは「知らない言葉」を調べる時間でした。
記事を書いていると、「なんとなくわかっているつもり」の言葉が実はちゃんと理解できていない…ということがよくありました。
たとえば「パーマリンク」とか「インデックス登録」とか、わかるようでちゃんと理解してないことが多くて…。
意味を調べようと検索しても、専門用語だらけの説明ページばかりが出てきて、読むだけで疲れてしまうこともありました。
そんな時に助けてくれたのが、AI──特にChatGPTでした。
今は、ChatGPTに「小学生にもわかるように説明して」とお願いすれば、シンプルな言葉でかみ砕いて説明してくれます。
しかも、そのまま「たとえばどういうこと?」と追加で聞けば、例え話や具体的な状況まで教えてくれるので、調べ物のストレスが大幅に減りました。
今までは、わからない言葉が出てくると調べるのに時間がかかって書く手が止まりがちだったのですが、今ではスムーズに進められるようになりました。
こういうところに**AIの“真価”**を感じています。
「知らない」を乗り越えるハードルがぐっと下がることで、記事を書くスピードも質も上がった実感があります。
■ 収益が出た「たった1記事」が教えてくれたこと
そんな中でも、ある記事だけが楽天で商品が売れて収益発生したんです。
数ある記事の中で唯一成果が出たその記事を振り返ってみたとき、明確な共通点がありました。
特別SEOを意識したわけじゃなかったけど、「自分のリアルな体験」をベースに書いた記事でした。
たとえば、ある家電を購入して実際に使った時の感想や、届いたときの写真、良かった点・気になった点を率直に書いたんです。
決して文章として完璧だったわけでもなく、むしろ「体験談としてそのまま語った」ようなラフな記事でした。
でも、その記事だけはクリック率も高く、そこから実際に購入されて収益につながった。
「リアル」があるだけで、読者の行動はここまで変わるのかと驚いたのを覚えています。
読者から見れば「誰かのリアル」がいちばん信用できるんだなと、実感しました。
そして、読者が求めているのは“情報”だけじゃなくて“判断材料”なのだとも感じました。
その判断材料は、意外と日常の中にある自分の体験や感情から生まれるものなんですよね。
この経験から、「うまく書こうとしすぎなくていい」「伝えたいことを素直に書けばいい」──そんな心構えが持てるようになりました。
■ 今日のまとめ
- アクセスがないときこそ、書く意味を見直すチャンス。どんな結果になっても「書いた経験」は必ず次につながります。
- AIに頼りすぎず、“自分の視点”を文章に入れること。読者が共感するのは、その人ならではの体験や気づきです。
- モヤモヤの正体に気づけたら、手はまた動き出す。言葉にできた瞬間、不思議と前に進むエネルギーが生まれます。
- AIは「わからない」を乗り越える味方になる。難解な用語や概念も、噛み砕いてくれることでスムーズに理解が深まります。
- 読まれる・収益につながる記事は、じつは“自分らしい記事”だったりする。背伸びしないリアルな声が、いちばん信頼されます。
こうして振り返ると、すべての「つまずき」がそれぞれ意味を持っていたことに気づかされます。
だからこそ、手が止まったときも「これは何かのきっかけになるかもしれない」と前向きに捉える視点が大切なんだと思います。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
もしあなたも「なんか最近手が止まってたな」と感じていたら、今回の話が少しでも励みになれば嬉しいです。
「自分もそうだった!」という気持ちは、きっと誰かの背中を押す力になります。
自分の歩みが、誰かのヒントになる。
そんなつながりが生まれるのも、書くことの醍醐味ですね。
ではまた次回の配信で!