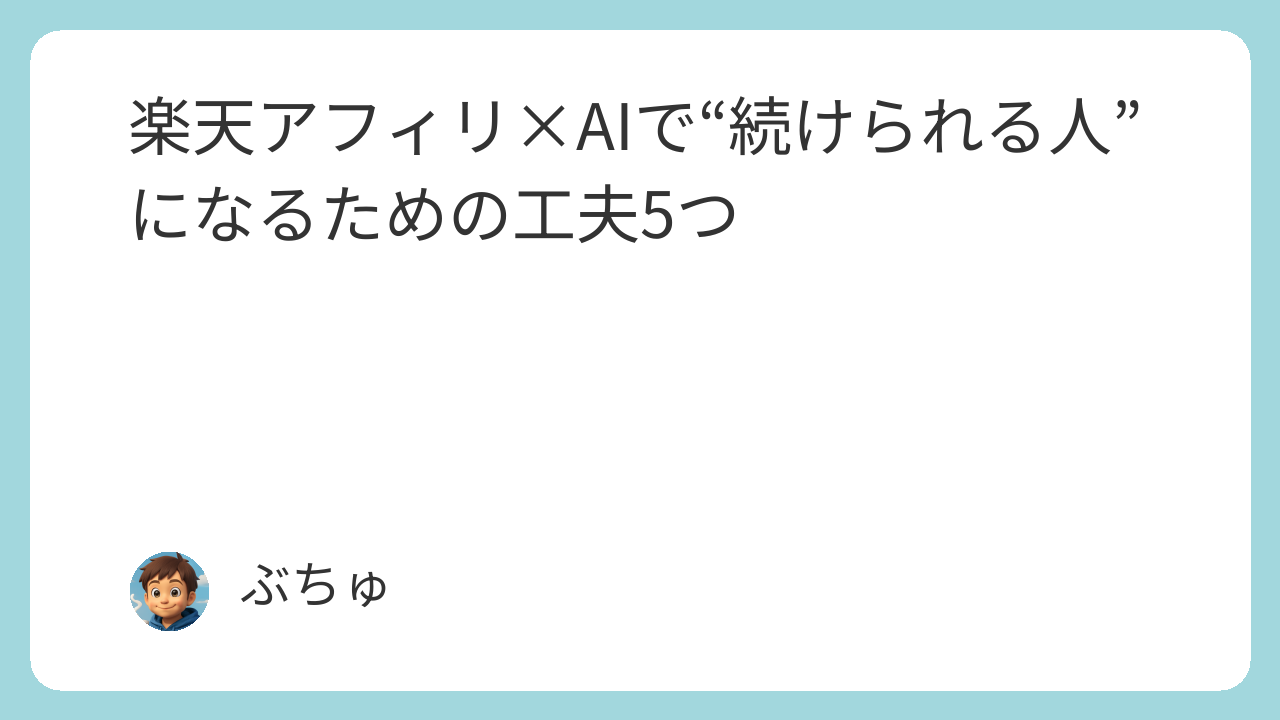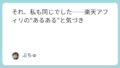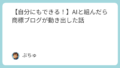こんにちは、ぶちゅです。
今回は「環境・習慣・継続の工夫」について、僕の実体験ベースでお話しします。
世の中にはさまざまなノウハウやSEO情報が出回っていますが、結局のところ大切なのは「行動しているかどうか」です。
手を動かしているだけで、もうその時点で他の大多数の人と差がついています。
だからこそ今回は、僕が毎日実践しているルーティンや考え方、そして続けるために取り入れている仕組みなどを、具体的に5つの視点からご紹介していきます。
1. 朝15分だけ楽天ランキングをAIに読ませてネタ候補を出すルーティン
毎朝の習慣として取り入れているのが、楽天ランキングの上位商品をChatGPTにざっと読み込ませ、その情報を元に商標系の記事で使えそうなネタ候補を3つ程度提案してもらうという軽い作業です。
所要時間はおおよそ15分程度で、コーヒーを飲みながら片手間にできるぐらいの気軽さがちょうどいいと感じています。
このルーティンの一番の目的は、「悩まない状態をつくること」です。
記事を書く前に「どの商品について書こうか」と迷ってしまうと、そこで思考がストップしてしまい、結果的に何も書かないまま1日が終わってしまうこともあります。
そこで、あえて朝一番に“ネタ選び”だけを済ませてしまうことで、その日の行動のスタートが格段に軽くなります。
大事なのは、「完璧な選択をしようとしない」ことです。
出してもらった候補を見て、ピンとくるものがあればそれでOK。
ピンとこなければEvernoteやNotionにメモしておいて、後日再チェックすればいいのです。
未来の自分のためにストックしておく、という意識で取り組むと、無駄がありません。
さらに、AIに出してもらったネタ候補に対して「この商品のレビューは何が強み?」「これに合うターゲットはどんな人?」などと追加の質問を投げかけることで、短時間でもかなり深掘りができます。
気が乗っている日は、そのまま下書きに入り込んでしまうこともあります。
こうした朝の15分間を地道に積み重ねていくと、気づけば1週間で10件以上のネタストックがたまっていた、なんてことも普通にあります。
そして、日によって気分が乗らない時でも「過去に集めたネタ」があるだけで、無理なく取り組むことができます。
つまり、朝の短い時間で“ネタがある状態”を日々キープできていれば、記事執筆のハードルはどんどん低くなっていきます。
結果的に、継続の土台として非常に心強い習慣になっています。
2. タイトルと見出しだけ先にAIに出してもらって着手のハードルを下げる
記事を書き始めるとき、最もエネルギーが必要なのが「最初の一歩」です。
頭では「書かなきゃ」と思っていても、白紙の画面を前にして手が止まる、という経験は誰にでもあるはずです。
そこで僕は、AIの力を借りて“着手のきっかけ”を作る工夫をしています。具体的には、以下の2つをChatGPTなどのAIに出してもらいます。
- その日の商標記事にふさわしい記事タイトル候補(できるだけ検索意図に合った表現で)
- H2・H3の見出し構成案(リサーチや想定読者を加味して)
この時点では本文はまだ書かなくてOKです。
あくまで「見出しの骨組み」だけでも先にあると、後から執筆に取り掛かるときにスッと入っていけます。
特に、まとまった作業時間が取れない日でも、この構成だけ用意しておくと、隙間時間で続きを書く準備ができている状態になります。
また、AIに見出しを作らせる際には、「どんなターゲットに向けた記事か」や「どんな検索意図に応えるか」などの前提条件を伝えるようにしています。
そうすることで、より精度の高い構成が出てきます。
慣れてくると、自分の中に「構成の型」が蓄積されていくので、それもまた次の記事への加速材料になります。
さらに、このやり方のもう一つの利点は「途中離脱への抵抗感が減ること」です。
人は“中途半端に途中までやった作業”の方が再開しやすい、という心理があります。
構成だけ作って中断した状態は、再開へのハードルが極端に低くなるんです。
実際にこの方法を取り入れてからは、「途中で止まっていた記事」にもう一度向き合うハードルが下がり、完成までこぎつけることが増えました。
そして一度書き終えた記事は、資産として残り続けます。
「一気に書き切らなきゃいけない」というプレッシャーを外してあげることで、結果的に“完成する記事の数”が増えるという好循環が生まれています。
3. 今日1つでも進んだらOKという思考が継続の原動力
やることが山積みで「今日はまったく進まなかった」と感じる日、きっと誰しも経験があると思います。
そんなときに「自分はダメだ」とか「全然できていない」と自己否定してしまうと、それだけで気持ちが沈んでしまい、次の日のやる気まで奪われてしまいます。
実は、この“できなかった感”こそが、習慣を崩す最大の敵だったりします。
だから僕が取り入れているのが、「1ミリでも進んだらOK」というルール。
これは、どんなに小さな行動でも「前に進んだ」と捉えることで、達成感を得られる考え方です。
たとえば、以下のような小さな行動でもすべてカウントします。
- ネタを1つだけEvernoteにメモした(2分)
- ChatGPTに1行だけ指示を送ってプロンプトの下書きを作成した(3分)
- 昨日書いた記事に1文だけ追記・修正した(5分)
- 売れ筋キーワードを1個だけリサーチした(4分)
これらは一見すると取るに足らない作業かもしれません。
でも「昨日の自分より1つ進んでる」と実感できるだけで、継続へのモチベーションが維持されます。
この「小さな前進を認める」スタンスに変えてからは、毎日のように「今日はOK」と言えるようになりました。
大きな作業ができた日はもちろん満足ですが、むしろ小さなことを積み上げる日が多いからこそ、無理なく継続できています。
さらに、進捗を可視化する工夫もしていて、僕の場合はGoogleカレンダーに「やったことメモ」をつけたり、1日の最後にEvernoteに「今日の前進ログ」として数行だけ残したりしています。
後から見返すと「こんなに地道にやってきたんだな」と自分を褒められる材料にもなります。
行動が積み重なると、自信が生まれます。自信が生まれると、継続がさらに加速します。
この好循環を回すうえで、「1ミリ前進ルール」は本当におすすめのマインドセットです。
4. 自分専用のAI指示テンプレをEvernoteにまとめている
ChatGPTや他のAIツールを日常的に使っていると、自然と「この指示、前も使ったな」という場面が増えていきます。
あるいは「以前うまくいったプロンプトがあったけど、どこに書いたっけ?」と探し直すことも。
そうした小さな手間が積み重なると、意外とストレスになります。
そこで僕は、AIに対して使っているプロンプトをジャンル別にテンプレート化し、すべてEvernoteにまとめて保存しています。
Evernoteなら検索もしやすいし、スマホからもPCからもすぐに確認できて非常に便利です。
カテゴリ分けの一例としては
- 楽天ランキングからのネタ抽出用プロンプト(毎朝のルーティンに使用)
- 記事タイトル&構成生成プロンプト(記事着手のハードルを下げる目的)
- セール前の準備リスト作成プロンプト(作業の抜け漏れ防止)
- 商標ワードリサーチ用プロンプト(商品名や型番から情報抽出)
- キーワード競合分析の簡易版プロンプト(SEO対策の第一歩として)
といった具合に、目的や用途に応じて細かく分類しています。
このテンプレ集を用意しておくと、作業を始めるときに「どんな風にAIに聞けばいいかな?」と悩む時間がゼロになります。
その結果、作業の立ち上がりがとてもスムーズになりますし、出力結果のクオリティも安定してきます。
さらに、こうしたテンプレはどんどん育っていきます。
使うたびに微調整したり、うまくいった表現を追加したりすることで、自分専用の“AI辞書”のようになっていくのです。
このプロンプト集の存在があることで、毎回ゼロから考えなくて済むというのは、精神的にもかなりラクです。
日々の時短にもなるし、何より「自分の武器が増えている」という安心感にもつながります。
特に副業や限られた時間の中で作業をしている人ほど、この“テンプレの仕組み化”は本当に強い味方になると実感しています。
5. セール前はAIに「準備リスト」を作ってもらう
楽天のお買い物マラソンやスーパーセールの開催が近づいてくると、アフィリエイターとしてはやるべきことが一気に増えて、何から手をつければいいか分からなくなることがあります。
準備不足のまま当日を迎えてしまい、「もっと早く動いていれば…」と後悔した経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
そんな混乱を防ぐために、僕が取り入れているのがAIを使った“事前準備リストの自動生成”です。
具体的には、ChatGPTに「次の楽天セールに向けて、商標アフィリ用の準備タスクをリストアップして」と依頼します。
すると、以下のようなToDo項目が出てきます。
- 過去の売れ筋商品のデータを見直し、今回も推せるかを判断する
- クーポンやキャンペーン情報の確認とリンクの更新
- 商品紹介ページのリンク切れチェックと最新情報への差し替え
- 特集ページの事前チェックと注目カテゴリの洗い出し
- 競合記事の確認と、差別化ポイントの検討
- 新しい目玉商品のリサーチと速報性のある記事化準備
これらをそのままチェックリストとして管理ツール(NotionやTrello、Google Keepなど)にコピーすれば、準備漏れを防ぎつつ、作業の優先順位もつけやすくなります。
さらに、AIには「このToDoを3日間に分けてスケジューリングして」といった依頼もできます。
自動的に効率的な進行計画を作ってくれるので、忙しい中でも無理のない作業配分が可能になります。
このように、セール直前に焦って一気に準備するのではなく、AIの力を借りて前倒しで“段取り済みの状態”を作っておけることが、精神的にも非常に安心感があります。
そして、きちんと準備できたセール期間は、やはり結果もついてきやすい。
アクセスも報酬も数字に直結するので、準備にかけた時間はそのまま“売上への投資”とも言えます。
AIに準備タスクを投げて、淡々と処理していく。
その仕組みを習慣化すれば、セールのたびにスムーズな流れを作れるようになります。
まとめ:小さな行動を積み重ねられる人が強い
どんなにすごいテクニックや知識があっても、行動に移さなければ意味がありません。
逆に、どんなに小さな行動でも、それを積み重ねている人には絶対に勝てません。
今回紹介したような工夫は、どれもハードルが低く、今日からすぐ始められるものばかりです。
まずは「1ミリ前進」でOK。自分なりのやり方で、無理せず楽しく継続していきましょう。
次回は、実際に僕が使っているプロンプトやテンプレートを、具体的に紹介できたらと思っています。
それではまた。今日も前向きに1つ進めていきましょう。