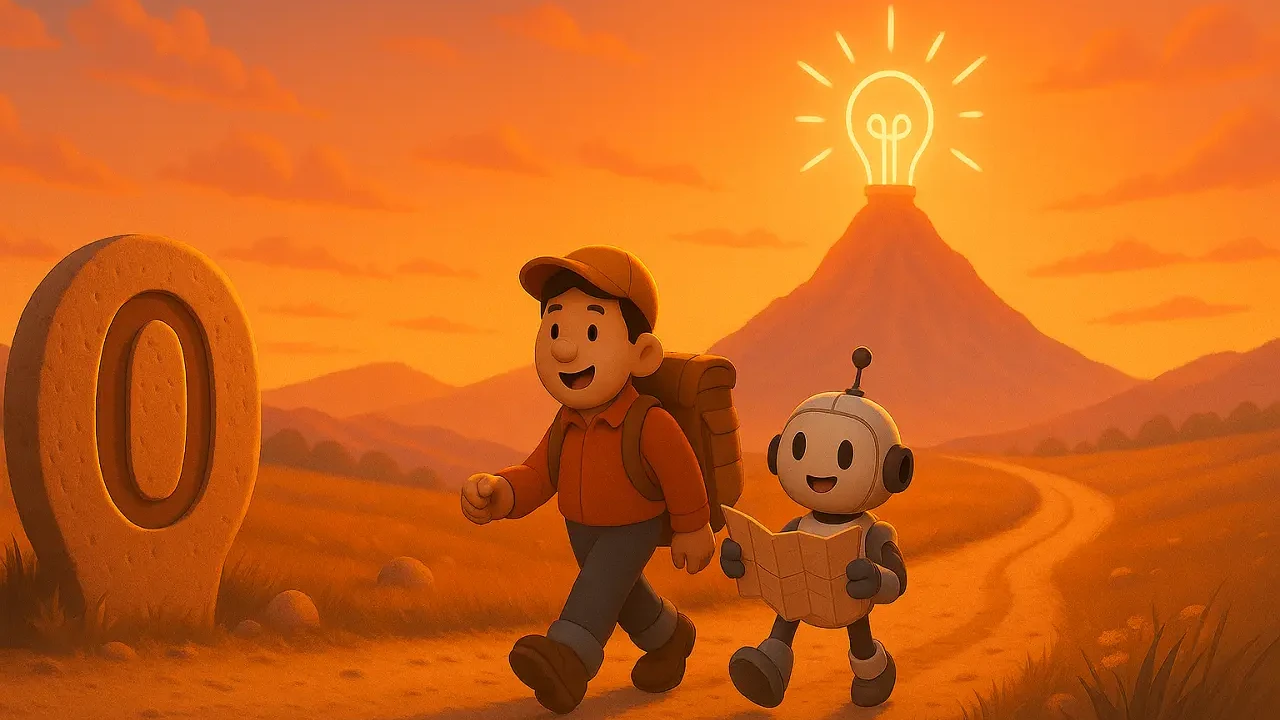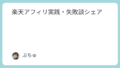今日は、たとえ収益がゼロの時期であっても、そこで止まってしまわずに前を向いて行動していくことの大切さ、そしてそんな時期だからこそ得られる貴重な気づきや視点を、できるだけわかりやすく丁寧にシェアしていけるメルマガをお届けしたいと思います。
日々の実践のなかで見えてきた発見や、AIとの対話を通して深まった学びを交えて、あなたの思考や発信のヒントになれば幸いです。
自分のブログって「どんな読者に刺さる?」をAIと一緒に棚欄ししてみた
これまでは、どちらかというと自分が「良さそう」と感じた商品についてだけを記事にしてきた系統でした。しかし、それだけだと、読者にとってのメリットや価頼感が伝わりづらいことが多く、結果的に「読者動動」を起こせていなかったなと、自覚するようになってきました。
そこで、ChatGPTに相談して「このブログの読者は、一体どんな人なのか?」「どんなシーンで、どんな時に読みたくなるのか?」といった解説を求めてみました。
すると、たとえば「定年のワーママ」や「一度は、評判を調べてから買い物をしたい」といった、情報収集型の読者働働が考えられそうな設定を、たくさん挙げてくれました。
そのようなペルソナが見えてくると、こちらとしても「その人に伝えたい」という意識を持って文章を書けるようになり、ここまでの書くのに比べても、単純に楽になり、伝えたいメッセージが明確になったことにより、文章の説得力も高まったように感じました。
こういった「読み手を意識する読者視点」は、直接の収益にはならなくても、長期的には結果を変えてくるはずだと思っています。
なぜ売れないのか→売る気がある文章になってなかった
売れない理由を、ずっと商品の魅力不足だと思っていました。商品の特徴やセールポイントが不完全なのか、もしくは対象者とはずれているのかなど、つい、商品側の問題だけに合理を求めてしまいがちだったのです。
でも、書き手側の文章をAIにチェックしてもらったことをきっかけに、大きな気づきがありました。そもそも、文章から「売りたい」気持ちや、読者に実際に利益があることを伝えようとする姿勢が、はっきりと出ていなかったのです。
そこでAIに「この説明では、読者は何に興味を持ち、どんな価値を感じるのか?」を問いながら修正指示をもらうと、ただの機能説明や個人的な感想ではなく、「こんな情報を知りたかった」「自分の問題を解決するヒントがあった」と思ってもらえる様な文章を意識するようになりました。
「なぜこの商品がいいのか」よりも、「なぜ読者にとってそれが価値があり、、何のベネフィットがあるのか」を言葉にする。そこに気を配るようになってからは、だんだんと読者反応もよくなっています。
読み手視点に立って伝える力を訓練する。そんな、説得力の覚醒になりました。
「クリックされる記事」の本質はタイトルより…
これは今日ふと気づいたことなのですが、アクセスがあった記事を見返していると、ひとつの共通点がありました。それが「サムネイル」の力でした。
たとえタイトルが淡くても、サムネイル画像が覚性を制し、覚えがあります。むしろ、その画像に誘われてクリックしてもらえたけケースもあり、その利上をあらためて実感しています。
さらに言うと、商品名を入れたタイトルだけだと、他の記事との区別化がなく、視覚的なインパクトも薄いのですが、他の記事に混ざり込んでもパッと覚えるようなサムネイルは、読者の気を引く大切な手がかりになると思いました。
これ、商品名イコールのタイトルを付けてるだけよりも、もっと大切な要素なのかもしれません。
今後の「ジャンル」をAIに相談した結果
これまでは、いわゆる大手サイトでも記事が多く上がっているような、いわゆる当たり前商品のネタに、どうしてもちからざるを得ない状態でした。ニーズはあるけど、こちらの記事は基本的に基本情報の繰り返しで、何か新しさや個人性を出すのが難しく、だんだん無理をしてる感覚が増していったのです。
そこでAIに相談して、ただの商品解説ではなく「自分の体験や評価を上手く繋げられそうな分野」は何か、また、「これからストレスなくねりやすそうな分野」を紹介してもらいました。
すると、たとえば「自分の作業空間にある家電」や「普段使っているグッズに系列するもの」など、近すぎて逆に覚らなかった分野に、光が引かれました。
なるほど、それなら既にユーザーの機持もあるし、自分の言葉で語りやすい。しかも、同じような環境にいる読者にとっても、それはイメージしやすいネタになりえるはず。そんな確信もわいて、だいぶ心が楽になりました。
セール以外の時期に売るには?AIに聞いたヒント
「オフ期って売れないよな…」とこぼしげたら、AIからの答えは、その言葉をひっくり返すようなものでした。
「オフ期にはオフ期の記事があります。セールに頑張ってもらうための準備をしたり、読者の興味をこちら側で作ることもできる」。
そんな指摘をもらい、「セールを倒さない言葉」で記事を構成する発想を教わりました。
例:
- 「思わずポチる」系:憩言なく想わずクリックしたくなるような引きのある表現。
- 「最後の一押し」系:もう一歩で買うけど迷っている人の背中を押す。
- 「今買わなくても、知っておいたほうがいい」系:情報を先に給与して、後の買い物に繋げるような演出。
これらは、直接にセールの話をしなくても、読者の興味や買い欲を継続させるための効果的なアプローチです。
こうした発想を素直に受け入れられたことで、これまでの「セールなんぼ」になっていた自分の発信に、新たな覚醒をもらうことができました。
セール予告に頻繁に頼りすぎていた自分にとって、この発想はまさに眼かから麻の目。これからの記事の締め方を見直す大きな覚点となりました。
収益ゼロ期。 この時期こそ、データを確認しながら、ゆっくり思考しながら「自分の次の拠点」を育てる時期だと思っています。
こんな気づきや実験を、記事の底強めとしても、メルマガとしても、同じように誰かの勉強になればと思って発信しています。