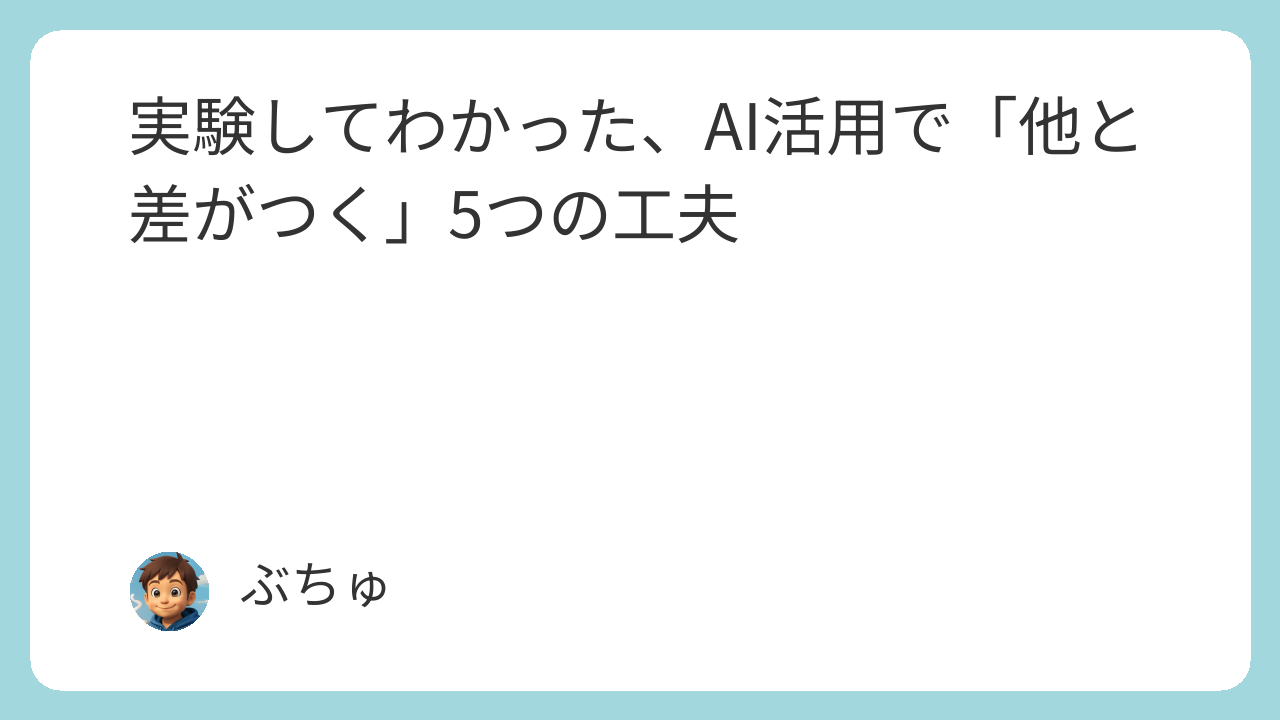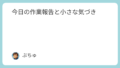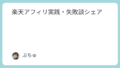こんにちは、ぶちゅです。
今日は、楽天アフィリ実践の中で、 「AI(ChatGPTやCanvaなどのツール)を使って、実際にやってみてよかったこと、役立った工夫、小さな発見」について、 具体的な実例を交えて5つご紹介したいと思います。
どれも決して大げさなノウハウではありませんが、 日々の作業の中で「これはいいかも」「もっと早く知りたかった!」と感じた、 いわば“現場で拾ったAI活用のヒント”です。
こういったちょっとした工夫の積み重ねが、 結果的に作業の時短や、記事の読みやすさ、さらにはクリック率にもつながるのではと感じています。
“みんなが同じような商品を扱い、似たような書き出しや構成の記事が並ぶ”中で、 どこかに「自分らしさ」や「読み手への気配り」をプラスできたら、 その小さな違いが、読者の反応や成果に結びつくはず。
そんな想いも込めて、今回の実験報告をまとめました。 あなたの実践にも、何かヒントになれば嬉しいです。
ChatGPTに「この商品の使い方別キャッチコピー」を出してもらったら秀逸すぎた
たとえばフライパンの商品。 ChatGPTに「この商品を、使うシチュエーションごとにコピーを変えて紹介したい」と伝えると、 「一人暮らし向け」「お弁当づくり向け」「キャンプ用」など、 具体的なライフスタイルを踏まえた角度から、ピンポイントでキャッチコピーを提案してくれました。
「朝の5分で1品完成、時短弁当派に最適」 「IHでも使える、ソロキャンパーの相棒」
…これ、自分では思いつかない切り口でした。
しかもそれぞれのコピーに「誰の」「どんな悩みを解決するか」が明確に含まれていて、 思わず「そのまま使いたい」と思えるようなものが多かったです。
こうしたシーン別キャッチコピーは、 記事の冒頭リード文だけでなく、見出し、ボタン前の導入文、 比較表の「おすすめポイント欄」などにも応用が可能です。
特に、見出しのバリエーションを複数パターン作りたいときや、 訴求ポイントをズラしたいときには重宝しています。
実際、記事を読んだあと「まさに自分にぴったりだと思って買いました」という 感想が寄せられたこともあり、 読者視点でのキャッチの重要性を改めて実感しました。
記事冒頭に「季節の導入」を入れてもらったら、グッと自然に
いきなり「この商品は〜」と始めるよりも、 ChatGPTに「今の季節に合わせた導入文」を書かせると、 記事全体の雰囲気が一気に柔らかくなります。
「まだまだ暑さが続く8月。キッチンに立つのも億劫になりますよね。」
といった自然な流れで始められて、 読み手の共感が取れるようになりました。
こうした“季節感を反映した導入”は、 単なるテンプレ的な書き出しよりも読者の気持ちに寄り添えるし、 「この人、ちゃんと今のことを考えて書いてるな」と感じてもらいやすくなります。
さらに、ChatGPTに対して「季節+読者層(例:30代主婦向け)」や 「季節+悩み(例:夏バテ気味で料理を手軽に済ませたい)」のように もうひと段階深い条件を伝えると、 よりパーソナライズされた導入文を出してくれるのも便利なポイントです。
実際、導入に季節ネタを入れた記事のほうが、 クリック率や滞在時間が微妙に良かったというデータも取れています。
冒頭の“つかみ”に悩んだときは、まずChatGPTに季節導入を頼んでみる。これは鉄板です。
「楽天の売れ筋=みんな書く」→じゃあAIにズラす角度を出してもらった結果
楽天市場の売れ筋ランキングに載っている商品は、 当然ながら多くのアフィリエイターが注目しています。 つまり、「商品を選ぶ段階ですでに競争が激しい」状態です。
「この商品、売れてるし自分も書いてみよう」と思っても、 いざ検索してみるとすでに上位にはライバル記事がズラリ。
そこで私は、ChatGPTに助けを求めました。 「この商品について、王道じゃない切り口を5つ出して」と投げかけたところ、 以下のような面白いアイデアが返ってきました。
・比較記事の“あえて2位を推す理由”に使う ・「買って失敗した人の声」から逆にメリットを浮き彫りにする ・他ジャンル(例:アウトドア×家電)で掛け合わせて紹介する ・商品が向かない人・使いこなせない人に焦点を当てて“逆張り”で語る ・型番違い・旧型との違いにフォーカスした「買い替え派」向け訴求
このように、“ズラし”の角度が出てくるだけで、 王道以外の視点からの切り口が一気に広がります。
特に面白かったのは、「マイナス評価を入り口にする」という視点。 一見ネガティブな内容から入ることで、かえって信頼感やリアルさが増し、 結果的に商品のポジティブな特徴を際立たせることができるのです。
また、ジャンルの掛け合わせ(例:アウトドア×家電)も、 ユーザーの使用シーンを明確に想像させる効果があり、 検索では拾われにくいが“刺さる読者”にピンポイントで届く可能性を感じました。
こういった角度の提示は、自分ひとりで悩んでいてもなかなか出てこないので、 AIとの対話によって、投稿の幅がぐっと広がった実感があります。
単独記事にするだけじゃなく、まとめ記事や比較記事、ランキング記事など、 記事構成そのもののアイデアにも波及してくるので、 「ネタ切れ気味かも…」と感じたときにもおすすめのアプローチです。
AIとCanvaで「アイキャッチ×タイトル」の整合性をチェックしてみた話
記事タイトルを「省スペース収納」としたのに、 アイキャッチ画像が「大容量!」だったことがあり…。
そのときは何気なく作った画像だったのですが、 あとから見直してみると「なんかしっくりこない…?」と感じる違和感がありました。 でも、制作者目線では慣れてしまっていて、 何がどうズレているのかはっきりと言語化できなかったんです。
そこでCanvaで作った画像とタイトルをセットで、 ChatGPTにそのまま投げて「この2つ、印象的に整合性あると思う?」と聞いてみたら…
「画像は“たっぷり収納”を訴求していますが、 タイトルの“省スペース”とは少しギャップがあります」
というズバリのフィードバック。 このように、AIは主観に左右されない視点で“言語化してくれる”のがありがたいポイントです。
加えて、「アイキャッチで伝えたい印象」と「記事の中身に沿ったタイトル」の両方を考慮したうえで、 どちらを修正すべきか、あるいは補足すべきかの判断材料にもなりました。
それ以降は、「タイトル案と画像案はセットでAIにチェックさせる」工程を、 投稿前のルーティンにしています。 一度テンプレートを作ってしまえば、毎回一から悩まずに済むので作業効率もアップしました。
作る側の目では気づきにくいズレも、 客観視してくれるAIに見せることで、 より説得力のある記事作りにつながっていると感じています。
商品名+キーワードをAIに渡して「ママ向け訴求」に変換してもらった結果
商品名「コードレス掃除機」+キーワード「吸引力」で、 ChatGPTに「ママ向けに変換して」と聞いたところ、 思わず「そのまま見出しに使いたい!」と思うような リアルで共感度の高いフレーズが次々と出てきました。
「お昼寝中の掃除もOK。音が静かで吸引力バツグン」 「片手でスイスイ、子どもを抱っこしたままでも使える!」 「朝の登園前にサッと使える、軽量コードレス」 「子どもの食べこぼしにもすぐ対応、パワフル吸引」
“ママの日常”をしっかりと想像した上での提案が並んでいて、 自分で一から考えるよりも、格段に速く・深くターゲットに刺さる言葉を得られました。
このとき特に効果的だったのが、 「○○なママに響くように」と具体的な指示を加えること。 たとえば「共働きで時間がないママ向け」「赤ちゃんがいる家庭向け」など、 より細かく指定することで、訴求の粒度がグッと上がります。
さらに、ChatGPTに「広告文っぽくせず、親しみやすく」といったトーンの指定も入れると、 より“口コミ風”“体験談風”のナチュラルな文面に仕上がるのもポイントでした。
“どんな人におすすめか”をChatGPTに明示するだけでなく、 その人がどんな生活シーンで悩んでいるか、どんな言葉で安心するかまで想定して伝えると、 AIは驚くほど自然なトーンでアウトプットしてくれます。
実際にこの記事は、CTR(クリック率)や滞在時間も良好で、 「自分のことみたいだったから読んだ」「こういう視点で紹介してくれると助かる」といった ありがたい反応もありました。
やはり“誰向けか”を明確にするだけで、 読まれる記事はグッと変わるのだなと実感しています。
少しずつでも、AIとの連携が上手くなると、 記事作成のスピードも精度も上がってきますね。 最初はおっかなびっくりで使っていたAIも、 「こう頼めば、こう返ってくる」というパターンが見えてくると、 まるで“優秀な外注パートナー”のような感覚になってきます。
記事の構成やタイトル、導入文だけでなく、 読者の共感を引き出す表現、ちょっとした言い回し、 さらには読者層の深掘りまで任せられるようになると、 自分ひとりで書いていたときにはなかった視点が生まれるのが面白いところです。
あなたも最近、 「これAIに頼んでよかったな」「思わぬアイデアが出てきたな」 と感じる瞬間、ありましたか?
もし「うまく活用できてないかも…」と感じていたら、 今回紹介したような小さな工夫から試してみるのもおすすめです。
次回は、「失敗から学んだAIの使い方」についても書いてみようと思います。 やってみたけど上手くいかなかったこと、 逆に「ここは人間の判断が必要だ」と感じたシーンなど、 リアルな試行錯誤も交えてシェアしますね。
ではまた、次回の配信で!