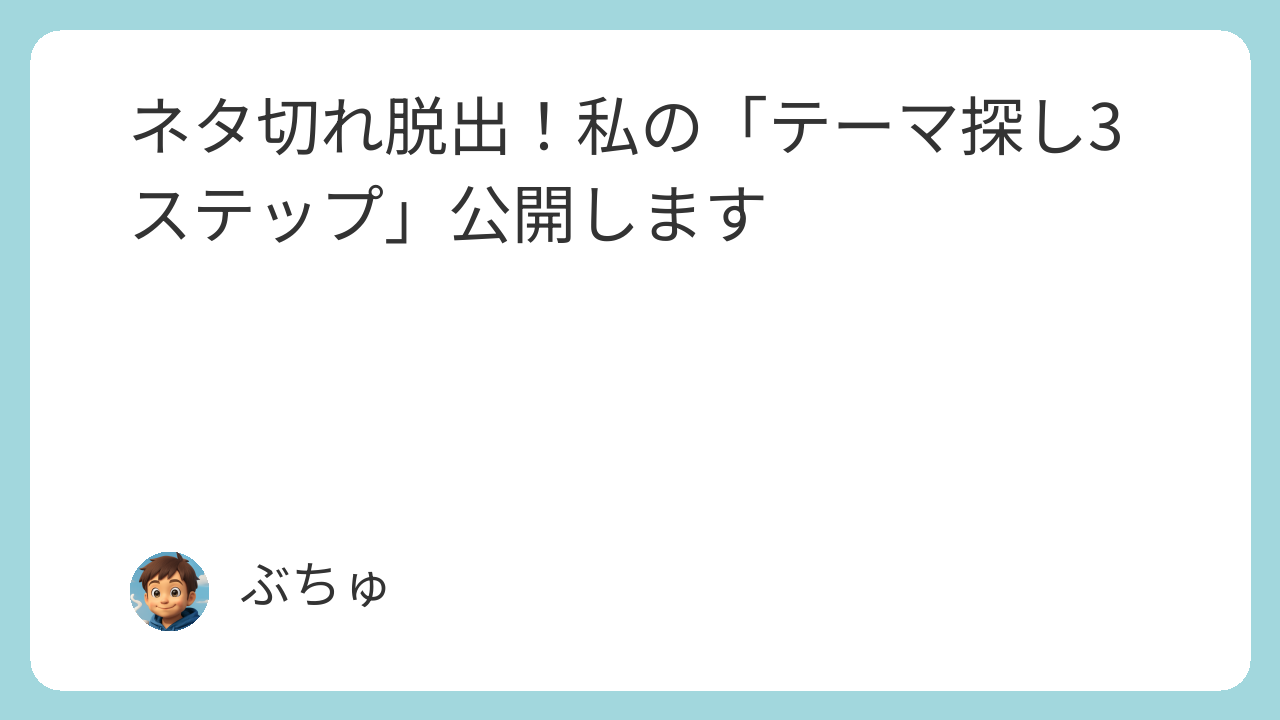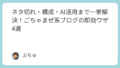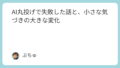こんにちは、ぶちゅです。
今日は「派手な結果はないけれど、確実に前に進んでるぞ」という、地味だけど大事な積み重ねについての実践と、それを通して得られた小さな気づきをいくつかシェアさせてください。
劇的な変化や爆発的なPVアップではないけれど、「これはあとで効いてくるかも」「次に活かせそう」という発見がありました。
きっと、同じように日々コツコツ作業している方のヒントにもなると思います。
✅ ChatGPTと一緒に、3記事仕込みました!
今日は比較的時間がとれたので、思い切って3記事分の原稿を一気にまとめて作成してみました。
普段は1記事仕上げるのにけっこうエネルギーを使うのですが、今回は「量を意識して進める」ことを目標にして取り組みました。
とはいえ、すべて自力でやったわけではなく、「ネタ出し→構成→本文」のプロセスはほとんどChatGPTの力を借りました。
例えば「〇〇というキーワードで構成案を出して」と頼めば、すぐに3~5パターン提案してくれたり、「この記事のリード文を考えて」と指示すると、読者の興味を引く導入を何通りも提示してくれます。
その中から自分の感覚に近いものをベースに、手を加えていくスタイルです。
改めて感じたのは、「ゼロから自分の頭で全部考えて書く」のと、「AIの力を借りながら進める」のとでは、作業スピードも精神的な負担も大きく違うということです。
もちろん、最終的に自分の言葉で整えて、読者に伝わる文章に仕上げる作業は不可欠。
でも、“書き出しまでのハードル”を一気に下げてくれる存在として、AIは本当に心強い味方だと実感しました。
この調子で、今後も定期的にまとめ書きしてストックを増やす流れを作っていきたいなと思っています。
✅ ネタ切れ…から脱出した!私の「テーマ探し3ステップ」
「もう書くことがない…」と感じる日ってありますよね。何を書こうかPCの前でうーんと唸って、気づいたら時間だけが過ぎている、なんて経験は私も数えきれないほどあります。
でも今日は、ちょっとした工夫でスムーズにネタ探しができたので、私なりの3ステップをシェアします。
- 過去記事をざっと見返す
まず最初にやったのは、これまで書いた記事をざっとチェックすること。「このテーマ、他に切り口ないかな?」とか「この部分だけで1記事書けるのでは?」といった視点で見ると、意外と使えるネタが見つかります。特に反応がよかった記事や、自分が書いていて楽しかった記事は要注目。 - 検索欄にキーワードを入れて関連ワードを拾う
次に、ブログの検索欄やサジェスト機能を使って、キーワードを打ち込んでみました。すると、関連語や組み合わせ候補が出てきて「これとこれを絡めたらおもしろいかも」と思えるアイデアが浮かびます。まさに「ネタは検索から生まれる」感覚です。 - ChatGPTに「このワードでブログ案ちょうだい」とお願い
最後に登場するのは、頼りになる相棒・ChatGPTです。ピンポイントのワードを与えて「このテーマでブログネタを10個出して」と依頼すると、しっかり候補を返してくれます。その中から「これなら書けそう!」というものをピックアップして使いました。
この3ステップを踏むことで、5~6個はすぐに書けそうなネタが見つかりました。
特に自分の過去記事の“横展開”は、思った以上にヒントの宝庫です。
「一度書いたから終わり」ではなく、そこからさらに深堀りや派生ができるという気づきが、大きな収穫でした。
✅ 「この記事、なぜ反応よかった?」を分析してみた
最近アクセスがじわっと伸びている記事があって、なんとなく「よさげだな」と流してしまうのではなく、今回は少し立ち止まって、その理由を自分なりに丁寧に分析してみました。
まず注目したのは、タイトルの工夫です。
記事のタイトルには、読者が検索やSNSで目にしたときに「これは自分のことかも」と思えるような、“悩み系ワード”がしっかり入っていました。
具体的には、「〇〇できない」「△△のコツ」など、読者の関心を直接引くフレーズです。
次に、記事の冒頭部分。ここでは「この記事を読むことで、どんな悩みが解決されるのか」「どんな情報が得られるのか」が、非常に明確に書かれていました。
結論を先に出すことで、読者の離脱を防げていたのかもしれません。
情報の粒度もちょうどよく、難しすぎず浅すぎず、という絶妙なバランスでした。
さらに、画像の工夫も見逃せません。Canvaで作成したシンプルなアイキャッチに、余白を多めに取って文字をくっきり見せるデザインにしていたのですが、それがスマホ表示でも見やすく、クリックを促す役割を果たしていたようです。
背景にごちゃごちゃした模様がないことで、視覚的なストレスも少なく感じられました。
こうして分析してみると、自分なりの“当たりパターン”が少しずつ見えてきます。
今後の記事作成にもこのパターンを意識的に取り入れていけば、再現性のある成果につながるかもしれません。
✅ アイキャッチの作り方をちょっと変えてみた
今日は初めて「テンプレを固定せず、都度テーマに合わせて配色&フォント変更」を試してみました。
これまでは時短の意味も込めて、ある程度テンプレート化したデザインを使いまわしていたのですが、最近少しだけ“いつも同じに見える感”が気になっていたんです。
そこで今回は、記事の内容に合わせて背景色や文字色、フォントの雰囲気まで思い切って変更。
たとえば少しポップな内容のときは明るめの色と丸ゴシック、真面目寄りの記事のときは落ち着いたトーンと明朝体を使ってみました。
すると…**自分で言うのもなんですが、見た目がグッと洗練された感じに!**デザインにちょっとひと手間かけるだけで、印象ってこんなに変わるんだと驚きました。
しかもその変化によって、書いた記事自体にも愛着が湧いてくるんですよね。
「ああ、これ私が丁寧に仕上げたんだな」って感じがして、次の作業へのモチベーションにもつながりました。
テンプレートは効率化においてはとても便利ですが、ときにはその枠を外して“自分なりの見せ方”に挑戦してみることも大切だなと感じた1日でした。
「ちょっと違うことを試してみる」って、案外モチベUPにもなるんですね。
✅ 作業時間30分の日、私がやったことは…
今日はまとまった時間がどうしても取れず、気づけば作業にあてられるのはたった30分のみ。
正直なところ「今日は無理かな」と思う瞬間もあったのですが、それでも「何か一つでも前に進めたい」と気持ちを切り替えて、短時間でできることに集中して取り組みました。
まずやったのは、ChatGPTで構成のラフを出すこと。キーワードだけ入力して「このテーマで構成案を出して」とお願いすると、数十秒で3~5パターンを提示してくれました。
そこから自分の感覚に近いものを1つ選んで、見出しだけでも整理しておくことで、明日以降の作業がぐっと楽になります。
次に、過去記事のタイトルを1つだけリライト。これも侮れません。
わずかな文言の修正でも、クリック率が上がることがあります。
タイトルを見直すだけで「読んでみよう」と思わせる工夫ができるので、短時間でもやる価値ありだと感じています。
最後に、記事用の画像を1枚作成。Canvaを使えば5分ほどで形になりますし、見た目の印象アップにもつながります。
あらかじめ画像ができていれば、本文を書くときのモチベーションにもつながるので、非常に効率的です。
こうしてみると、30分でも意外とできることはあるものですね。
「少しでも前に進んだ」という実感が、次への原動力になると強く感じた1日でした。
最後に
毎日すべてが順調に進むわけではないし、思い描いた成果がその日に現れることはむしろ少ないかもしれません。
モヤモヤしたり、思うように手が動かなかったり、時間が取れずに手付かずで終わってしまったり。そんな日も当然ありますよね。
でも、そういう日でもふと立ち止まって振り返ってみると、小さな「気づき」や「学び」は必ずあるはずです。
たとえば、「今日は手を動かせなかったけど、次に優先すべき作業が明確になった」「このツール、今度試してみようと思った」「疲れたときはこうやって切り替えよう」など、ほんの些細なことでも構いません。
その“気づき”こそが、明日以降の行動のヒントになり、積み重ねれば確実に自分の中に力として蓄積されていきます。
結果や数字には表れにくいけれど、内側ではちゃんと前進している感覚。私はそういうものを、とても大切にしています。
もし「今日は何も進まなかったな…」と感じたとしても、自分にこう問いかけてみてください。
「今日の小さな気づき、1つでもあるかな?」
きっと、何か見つかると思いますし、その1つが自分を支える土台になっていくはずです。
では、また次回のメルマガでお会いしましょう。日々の積み重ねを、これからも一緒に大事にしていけたら嬉しいです。